| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
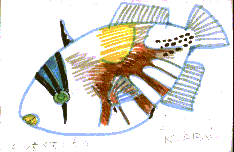 |
| 新井克彦画「ムラサメモンガラ」 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
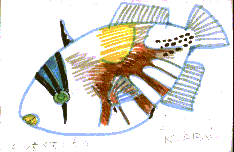 |
| 新井克彦画「ムラサメモンガラ」 |
1999.6.1(火)
2週間ぶりの徹夜で、明けて寝てました。夕方起きて、ベイスターズの阪神戦を見ながら書いています。ガックリしています。内容が良くない。エラーで自滅なんて信じられないんですが、最後まで応援しようと思います。
で、結果は7:2の完敗。ガクッ。
○秦恒平氏『湖の本』エッセイ18
中世と中世人(一)

1999.5.1 東京都保谷市「湖(うみ)の本」版元刊
日本ペンクラブ電子メディア対応研究会の秦座長からいただきました。この本の半分を占める「中世文化の源流」というエッセイは、1974年にNHKラジオの市民大学講座で放送した内容です。その後、平凡社刊『中世と中世人』に収められたそうです。
それを復刊したのが、この本です。秦さんはご自分の著書の復刊を『湖の本』を通して行っています。出版社がなかなか復刊してくれないので、業を煮やして始めたそうです。日本の出版文化を考える上でも、秦さんの行動は貴重な提言だと思います。
「中世文化の源流」は、非常に示唆に富んだエッセイです。私はほとんどの日本の中世には興味がなくて、むしろ世界史に目が向いていたんですが、この本を読んで考え方が修正させられました。日本の中世というのは、現代を考える上でも重要な位置を占めているんですね。
たとえば「寄合」という言葉があります。都会ではほとんど死語になっているかもしれませんが、私の実家(静岡県御殿場地方)や現在の住所(神奈川県南足柄市)のような田舎には生きています。まあ、言葉は「自治会総会」だとか「PTA委員会」などになっていますが、基本は「寄合」だと思います。特に自治会の役員会などは「寄合」と称して、私なども家を出ます。
この「寄合」の発端が中世だと秦さんは説きます。特に文芸に多く、連歌、茶などがさかんに「寄合」を行っていたそうです。しかもそれは単なる「寄合」ではなく、それを通じて権力への抵抗力をつけて行ったと解説なさっています。「権力への抵抗」ということでは、むしろ現代よりも自由だったのではないか、とも続けています。
なるほど、言われてみると身の回りで何気なく使っている言葉が、実は中世から続いているんだというのは、たくさんあるのかもしれませんね。言葉もそうだし日本人の考え方の基本に、「中世」はどっかりと腰をすえているのかもしれません。
このエッセイは、私ももう少しじっくり勉強しようと思いますが、他にご希望の方がいらっしゃったら、このホームページに秦さんのホームページもリンクされていますので、そこからご注文ください。定価は1900円で、送料100円です。
○大塚子悠氏詩集『風の駕籠』

1999.5.22 詩画工房刊 1800円
村人は灯籠に夜毎火を灯す
家族の人数の日を灯し続け
次に渡すのである
いつの頃からか続く。
日暮れの道に
安らぎの火と灯る
何事もない村に
何事もない幸せを灯して光る (「常夜灯」第二連)
これは面白いと言うか、素晴らしい風習ですね。大塚さんは兵庫県にお住まいの方です。私はとんと西のことは判らないんですが、万葉の頃から続いている土地のようです。
聖地の入口の石灯籠に
今日も火が赤い (同・最終連)
とありますから、今だに続いているんでしょうね。事実かどうかは問題ではありません。これをとらえた詩人の目に感嘆します。そこに住む人々への愛情こもった視点は、そのまま詩人の精神を表しており、この詩集の健全さを代表する作品だと思います。
「雲に遊ぶ」という作品は「朝焼け」「寝転んで」「雨雲」「夕立」「秋」「ほうき雲」という六つの小品から成り立っています。少年の日の回想を中心とした作品ですが、素直で、変な飾り立てがなくて、好感のもてる組みたてです。大塚子悠さんという詩人とは、おそらくお合いしていないと思いますが、穏やかな方なんだろうとの印象を受けました。
○個人詩誌『色相環』1号

1999.6.1 神奈川県小田原市 斎藤央氏発行
20年ほど前から、同じ地方に住んでいるということもあって注目している若手の詩人です。1997年に出版した詩集『不在の岸』は、様々な新人賞にノミネートされました。その彼が個人誌を発行したのですから、心より応援します。
昨夜 おまえが痛むと言った 乳輪のあた
りが隆起して 女のからだになりかけている
のがわかる 幼さが残るおまえの小さな胸に
揚羽蝶が静かに翅を休めている いつの日か
ふいに 揚羽蝶はおまえの胸から飛び立つだ
ろう おまえは驚いて蝶のゆくえを目で追う
だろう 蝶がおまえ自身だと気づくまでにど
れだけの時間がかかるだろう (「紫陽花(薄青)」第二連)
同じ年頃の娘をもつ私としては、よく判ります。男親から見た娘というのは本当に不思議な存在です。しかし、この作品はもう少し気をつけてみなければなりません。なぜ娘が男である作者に胸の痛みを告げるかということに注意しないと、この作品のほんとうの良さが半減すると思います。
おまえが忘れていったままの
薄藍色の洋服
両の袖のあいだに
忌まわしい月日はたたまれて
虚ろになった暮らしの
湿った匂いを包み込んでいる (「薄藍」第一連・部分)
「おまえ」というのが、離婚した妻のことです。これがあって初めて娘さんの置かれている状況が理解できます。ここからもう一度前の作品に戻っていただければ、その良さが十分に理解できると思います。
不幸なことですが、結局それが詩人を強くします。前出の『不在の岸』で斎藤央さんは、詩人として大きく飛躍しました。その背景には「薄藍」があったわけです。こんなことを臆面もなく書くのは、私も離婚経験者であることを蛇足ながら付け足しておきます。
[ トップページ ] [ 6月の部屋へ戻る ]