| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.1.14(月)
詩の雑誌『詩と思想』の新年会が新宿プチモンドでありました。ここのところ毎年出席させてもらっているんですが、昨年は風邪で当日欠席になって迷惑をかけたので、今年はどうしても出席したいと思っていました。幸い、風邪にもかからず出掛けられました。
新年会では毎年「詩と思想新人賞」の贈呈をやっています。その様子を写真に撮ってくれと編集部から依頼がありましたので、ニコンF70を持っていきました。でも仕上りはイマイチでしたね。ストロボの発光距離が思ったより短い。6mは届くと思いましたけど、ちょっと足りないな。4mぐらいに近づかないと無理そうです。純正のストロボじゃないから、少し余裕を持たないといけないようです。あっ、そうか、ストロボに拡散カバーを着けたのがいけなかったのかな。
 |
写真はデジカメで撮ったものですけど、これも光量が足りないな。モデルは第10回詩と思想新人賞受賞の方です。日本詩人クラブの会員でもあり、1〜2年に1度挨拶をする程度の方ですが、いい人です。こういう人が賞をもらうと、こちらまでうれしくなりますね。作品ももちろんgoodです。
| ○詩誌『飛揚』34号 |
 |
| 2002.1.7 東京都北区 葵生川玲氏発行 500円 |
日記/米川 征
見るべきものを見る
聞くべきものを聞く
つきることだけの
いやな時間の昼がつづく
だから
見るに値しないものを観る
聞くに値しないものを聴く
至福の夜がくる
ガス靄のカーテンを
地上の風景にひいて
昂揚して
個室は
恥ずかしい夢をみることもゆるす
日記を書く
特集「日記」の中の作品です。4連目に惹かれましたね。「見るに値しないものを観る」って、まるで詩を見ているようじゃありませんか。無用の長物、詩はそうであるべきだ、なんてつい力説してしまいそうです。もちろん作者の意図はそんなところにはないと思いますがね。
第1連は会社の仕事でしょうか。見る義務があり、聞く義務があるものをとりあえず無難にこなす。確かに「いやな時間の昼」です。それに対して「至福の夜」。「ガス靄のカーテン」や「恥ずかしい夢」はなかなか意味深長ですが、ちゃんと「日記を書く」へつないでいく。力量のある詩人だなと思います。これだけ具象をイメージさせて抽象化できる詩人はなかなかいないと思いました。
| ○故・西村皎三氏詩集『遺書』 |
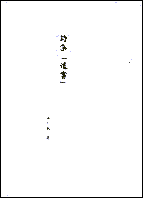 |
| 1940.9.13初版 1944.3.20再版 揚子江社出版部発行 1円80銭+特別行為税負担5銭 |
今月初めに親しい女性の友人から、次のようなメールをいただきました。
<この冬休み、私は、西村皓三という昭和15年頃に戦死した詩人の『遺書』という詩集を、それも、コピーもできないくらい紙の色が変わり、ちょって触っても、ぼろって、くずれそうなのを、ワープロで写して過ごしました。(中略) 戦争にいくということは、どういうことか、戦争から還るとはどういうことか、静かに知った感じがしました。>
考えてみたら、私は戦争中の詩人の、しかも軍人の詩集を読んだことがないことに気付きました。それにこの方の「戦争にいくということは、どういうことか、戦争から還るとはどういうことか」という文章にも惹かれました。そういう視点が欠如したいたなと思った次第です。そこで厚かましくもコピーを送ってくれるように頼んだのです。それで手に入れたのがこの詩集、正確にはワープロのコピーです。従って上の写真の表紙は現物ではありません。友人が一番表にしていたものを詩集の表紙として代用しました。
そしてコピーに同封されていた手紙には次のように書かれていました。
<私がこれを写すきっかけになったのは「小鳥」という詩にはげしく打たれたからです。それ以前に読んでいた詩は、あまりにも残酷なことをありありと映しているものが多く、読むのにつらかったときにこの詩を見ました。>
残酷な詩の代表としては、次の作品があげられると思います。
活火山
昨夜
くらやみの底でぶっぱなした便衣兵が畦水のなかに
のけぞっている。破壊された橋梁のやうに。
ポカンと開いたその口のなかには
水すましの輪がゆるく ひっそりと伸び縮みし
虚空をつかんだ腕のあたりは
藻の花が点々と白く。
それがおれの左側。
右側には
もうひとりの必死の足跡が
草に滑り
溝の縁を赭く削って
おそらくは世界的選手でも飛びおほせぬ歩幅を
それこそ一生一度の跳躍で
遠く朝靄の奥に消えている。
野菜畑を途轍もない巨きさで。
ここは廣東の郊外、
茫漠たる稲田と野菜畠のうちつづく風景を
東西に断ちきって
とある野道の
芒の穂かげに
野糞はおれの姿をそのまま
凝然と脚下に蹲っている。
朝まだき野草の青々溌刺たるを ぐいと抑へて
ガッシリと大地に跨り
かすかに白く煙を吐き。
その堂々たる逞しさ!
愛すべき己れの分身!
ふと おれは
その溶岩いろの凝然たるものの中に
われわれを哺くんで来た日本の底を流れる火山脈の
剣の尖をみた。
突如として火焔天に冲し
山容をくだき
今はしづかに 白くゆるやかな噴煙を
大虚のうちになびかしている活火山の
満ち足りた虚脱のなかに
青磁いろの敵地の夜あけに
今 おれの心臓弁は
悠然と朱色の口をあけっぴろげている。
昭和15年頃に戦死、ということからも判りますように、まだ敗色を知らない軍人、しかも航空隊の主計長と副官を兼務するという将校だった詩人の、一面的な戦場描写と言えるかもしれません。この感覚は戦争という極限状態の中でも、常勝気分の勝っていた時期だけに全編に現れています。しかし所詮は人殺しの戦場。精神が穏やかであろうはずがないと思います。そんな中で書かれたのが件の「小鳥」だったのでしょう。
小鳥
はげしき空襲より帰りしを迎えて−
生きて帰ったといふことは
なぜ、こんなにも落莫たるものであらうか
飛行服もぬがず
ひっそりと 木かげに黙ってしゃがんで
自分の小鳥に餌をやっている
草の葉を
いつもよりも細かくちぎって
それがなくなってしまふと
草色に染んだ自分の指先をたベさしている
もちろん私には戦場の経験などなく軽々しいことは言えませんが、この気持は判るような気がします。友人の女性が「はげしく打たれた」ということも理解できるように思います。これを書けるというのは、やはり詩人なんだなという思いもします。
時代の波の中で軍人になり、詩人であり、人を殺し、そして自らも戦死していくということはどういうことなのか、正直なところ現在の私には大き過ぎて考えがまとまりません。しかし、日本が戦争協力体制に入ってしまった今、現実の問題として避けて通れない命題になるだろうという予感がします。どこまで迫れるか、この詩集を何度も読み返して考えいきたいと思います。
ちなみに、詩集の後記には「佐藤春夫氏、長谷川伸氏その外の方々に一方ならぬ御世話をうけた」とありました。
![]() (1月の部屋へ戻る)
(1月の部屋へ戻る)
![]()