| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.2.26(火)
1年ぶりに電子顕微鏡を扱ってみました。私の担当する製品に新たなものが加わりそうで、その試作品の表面・裏面・断面の様子を知る必要が出てきたためです。久しぶりでしたからちょっと緊張しましたけど、まあ何とか見られる写真を撮りました。うまく新製品として立ち上がってくれればいいのですけど…。この不況の折、そう簡単にはいかないと思っています。
| ○詩誌『環』103号 |
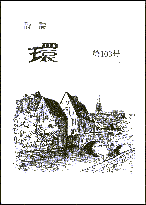 |
| 2002.2.10 名古屋市守山区 「環」の会・若山紀子氏発行 非売品 |
独り居/若山紀子
気が付いたら
風が吹いていた
裏の竹が撓んで
ひどい風だった
もう夕暮れが近かった
誰かに電話をかけたい
と思ったのだけれど
気が付いたら
そんな友達もいないのだった
父もいなくて
母もいなくて
兄もいなかった
弟も遠くて
いつの間にか夫もいなかった
愛することも出来なくて
おしゃべりすることもなく
とうとう
詩も書けなかった
気が付いたら
誰もいなくて
ひとり
ぽつんと部屋に坐っている
白い雲が
ゆっくりと空から降りてきた
ひゅるん ひゅるんと
風だけが生きていた
「気が付いたら/誰もいな」い状況では、なぜか「ひどい風」が気になるものですね。その心理をうまく表現している作品だと思います。「とうとう/詩も書けなかった」というのも判るような気がしますし「風だけが生きていた」という最終行も効果的だと言えましょう。孤独感を聴覚と視覚で表現し、身の回りの人たちを登場させることによって強調できた佳作だと思います。
| ○詩誌『梢』28号 |
 |
| 2002.2.20
東京都渋谷区 宮崎由紀氏発行 300円 |
十津川/日高のぼる
古文書では遠津川と記されているという
母の両親の生まれた奈良県吉野郡十津川村
一八八九年(明治二二年)の大水害で崩れ落ちた山が
ダム湖のなかへ半島のようにつきだしている
トビが頭上を舞う
ぬるい温泉につかりながら
空を見上げ故郷を離れた祖先を想う
原野の北海道に移住し
その並外れた苦労のなかで
少しでもいい暮らしができそうだと聞けば十勝へ移住し
さらに楽天地のように宣伝されたのか
一族そろって満州へ移住した
戦争で置き去りにされ
一年後帰国した母をはじめ
だれひとりとして十津川村へ足を踏み入れていない
山深い里は迎えてくれる親族もいない
村の物産販売所では
新十津川町の産品が成功したものの誇りのように
一角を占めていた
歴史が一族に染み付いていることを感じさせる作品です。教科書の中の歴史ではなく、体験としての歴史が明治以来、現在まで綿々と続いていて、その中のひとりとして作者に書かしめた、そういう印象を強く受ける作品です。十津川から出て、北海道、十勝、さらに満州へ、そしてその子孫が再び十津川の温泉を訪れるという、遺伝子の回帰のような人の動きにダスナミックさも感じています。当事者からは〝ダイナミック〟などという言葉は不遜の謗りを受けそうですが、血の強さのようなものを感じています。
| ○詩誌『木偶』49号 |
 |
| 2002.2.25
東京都小金井市 木偶の会・増田幸太郎氏発行 300円 |
死が見えるようになって来た
人の命が樹木のように見える
無数に立ち並ぶ大地にすさぶ林
風がどこからともなく撫ぜている
死が突然に訪れることは決してない
偶然が訪れようとも
そこに立ちはだかる因果な事象が見えてくる
偶然こそ必然にいたる道である
死が見えてくる
生きているものの中に確実に育ちながら
自立した機能を振りかざし、あたかも他人のように
わがままを主張するのである
だが、死は最もな理由を残している
われわれはその不動のかたちに
安らかさを見出して安堵するのである
こんなにも晴れた晩秋のときにも
アメリカはアフガンに
虱つぶしのように爆弾を落としている
かって、べトナムを焦土にしたように
アメリカの自由と正義の偏狭は
他国にとって迷惑である
紹介した作品は増田幸太郎さんの「ホロホロホロロ 秋が逝く」という詩の一部分です。300行を越える作品ですからすべてを紹介しきれず、一部となった無礼をお詫びします。
作者が樹木や自然と対話している状況下での作品です。死を見つめ、死の必然と偶然を思考する中で、突然、アフガンの爆撃が出てきて驚きますが、しかしそれは決して乖離したものでないことにも気付かされます。すべてを含有する詩人の眼があります。
そんな、すべてを言い尽くしたいという思いが長い詩になっていのだろうとも思います。おそらく、それでも言い尽くせないという思いも伝わってきます。長くなる理由の一端が判る部分として紹介してみました。
| ○遺稿集『藤井脩三作品集』 |
 |
| 2002.2.25
東京都千代田区 小学館スクウェア刊 非売品 |
副題が「1958~1999」となっており、2000年1月に亡くなった『帆翔』同人の藤井脩三さんの遺稿集です。1958年発表の自伝的な小説「死の殻」と唯一の詩集『蒼鬱の季節』からの抜粋、『帆翔』での発表作品が主になっています。仲間たちの追悼文、三人のお子さんの「あとがき」もあって、皆から好かれた詩人だったことがよく判ります。
黒い時間
悪夢の中の二重夢に身もだえるとき
現実は蜃気楼のたゆたい
夢中の実在を信じられますか
とはいえ
水をはじき散らす若い娘たちの声に
したたかな深傷(ふかで)が濡れてしぼんだ
「出口なし」とつきつめた私の心は
虚妄の門に向っているのを知らない
カツカツと足音を響かせる石畳には
もう私の影はない
かつて拘禁されたとき
深い生硬な眠りから覚めると
白茶けた洞穴に横たわり
まがまがしいけだものの「記憶」が
ジャッカルが私を窺っていた
(その後の持続睡眠療法はよかったのかしら?
ヘア・ドクトル)
膨張した灰色の脳のひだから
私の愛(かな)しい黒い時間が
インク消しで氾濫させられて
でもまあいじましい痕は残っている
詩集『蒼鬱の季節』に収められた作品で、「朝日ジャーナル」にも掲載された作品のようです。仕事で北アフリカを旅したときの作品と思われます。夢と現実のあわいを描いているような不思議な魅力にとりつかれます。ご冥福をお祈りいたします。
![]() (2月の部屋へ戻る)
(2月の部屋へ戻る)
![]()