| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.4.4(木)
うれしい便りが届いた。青森県弘前市の瀬川紀雄さんからのものである。今年1月21日に発売された第一短編小説集『道端に風光り』の、新聞書評のコピーが入っていた。私がご本人に依頼しておいたものだ。世間では件の小説集をどのように評価しているのか、それを知りたかった。書評に取り上げられるくらいだから当然かもしれないが、あたたかく読まれていた。うれしかった。
2002.2.19付の「陸奥新報」では、弘前市の詩人・芳賀清一という方が作品「部屋」「道端に風光り」について〝他人の心をうかがい知ることができる小説家の不思議な能力に感動した〟と書いている。
2002.3.19付の「東奥日報」で、青森県近代文学館室長の齋藤三千政という方は〝静かなトーンで丹念に昔日の記憶をたどり、自然の情景の美しさを描くその筆力が実にすぐれている〟〝なによりもそのディテールの表現が見事だ〟と書く。
やはり見ているところは同じだなと思う。私の見方とも大きくズレていないので、それもホッとした。詩も書いて小説も書く人はそうそういるものではない。双方の力を持つ瀬川さんに、これからも期待している。
と、まあ、格調高い^_^;文章はこの辺にして、瀬川さん、良かったね。コピーありがとうございました。頼みもしないのにそういうコピーを同封してくる人がいるかと思うと、瀬川さんのようにこちらから頼まないと送ってくれない人もいる。それも書いておきたいですね、、、って、もう書いちゃった。一緒に「じょっぱり」を呑める日を楽しみにしています。
| ○詩誌『よこはま野火』42号 |
 |
| 2002.4.1
横浜市緑区 よこはま野火の会・真島泰子氏発行 500円 |
石ころ/浜田昌子
学校帰り
スキップして歩いていた私は
少年院の前で立ち止ってしまった
門の内で無言で立ち続ける母と子
無言ゆえに通過できない私
母親は少年の上着の裾を掴み
毬栗頭の童顔の少年は
両手をズボンのポケットに入れたままだった
無言の時の中で少年は石ころを蹴って
広い少年院の庭をかけて戻った
バウンドして門の外に飛び出た石ころを
追うようにして拾い懐に入れた母親
涙も笑顔も言葉もない別れ
母親は少年の蹴った石ころを懐に抱きながら
ふり返り ふり返り
真すぐな道を夕焼けの中で
黒い点となっていった
「少年の蹴った石ころを懐に抱きながら」帰る母親の気持が痛いほど判る作品ですね。「私」はおそらく小学生だったのでしょう。強烈な印象として残っていたのだろうと思います。それにしても「石ころ」を注目した小学生は、その頃から詩人の素質を見せ始めたのかもしれません。私の隣市にある少年院の、長い塀を思い出しながら拝見しました。もうとっくに成人したであろう「少年」とその「母親」の現在を思わないではいられない作品です。
| ○詩誌『叢生』119号 |
 |
| 2002.4.1
大阪府豊中市 叢生詩社・島田陽子氏発行 400円 |
待望の老人/佐山 啓
若い頃から
年取ることを
望んでいた
いま年寄りんなって嬉しい
人と競争して走らんでもええし
高いとっから飛び降りんでもええし
崖っぷちを歩かんでもええし
吊り橋よう渡らんでもええし
そんなとこ行かんかったらええ
嫌なことはなんも
せんでええ
できんでええ
へーんだ
なんていうのは
平成極楽トンボの
駆出し老詩人のたわごと
「仕事がなく、悔しい、悔しい」と
土木工事会社の前の
階段手すりにロープをかけて
夫婦で首吊り心中した
七十歳の老トラック運転手
1連から4連目までは、同じことを考えてる人がいた!と思って喜んで読みました。しかし、その後はキツイですね。確かにそんなことを考えているのは「平成極楽トンボ」なのかもしれません。現実に「夫婦で首吊り心中した/七十歳の老トラック運転手」はいると思います。その人たちのことまで考えると「いま年寄りんなって嬉しい」なんてことは言えない言葉なのかもしれません。だからどうせよ、というのではなく、そこまで視野を広げなさいと教わったように思います。
| ○個人誌『むくげ通信』9号 |
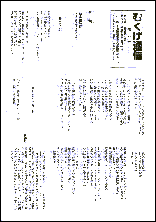 |
| 2002.4.1
千葉県香取郡大栄町 飯嶋武太郎氏発行 非売品 |
漢江/齋藤 ![]()
いかだがゆるやかに流れていた
川原にきぬたの音がはじけていた
私はひとり石を投げ
小石は力をためてつぎつぎと水を切った
不意に悲鳴がおこり
砂原に脚をとられながら女がかけて来た
はげしい言葉が投げられ
血のにじむ手が突き出された
私はその国の言葉を知らなかった
きぬたをほうり出して
あちこちから女が立ち上がった
私はあやまることをしっていたのに
私はそれをしなかった
この作品は何度か見たことがあります。最後の2行が印象に残っています。「漢江」で投げていた石が「女」に当り、抗議を受けたが「私はあやまることをしっていたのに/私はそれをしなかった」という不可解な詩です。怪我をさせてしまったのだから謝るのは当然のことです。私は齋藤さんを存じ上げていて、温厚な紳士の齋藤さんがどうしてこういう作品をお書きになったのか不思議でした。
その回答がここに、次のように書かれていました。
<無二の詩友であった崔華国でさえも、この詩を読んだ瞬間、ぎくっとした。「何故?この善良な少年が善良な女達に、誤って犯した禍に対して謝らなかったのか、不思議でならないばかりか、一種裏切られた不愉快さが先走った。」と述べるほどであった。しかし、よく考えてみると、これはやはり、斎藤特有のイロニーであったのだ。犯し蹂躙した日本が、被害者である韓国に、何ら謝っていないことに対する、辛辣な風刺であると気付いた。という。>
これで謎が解けました。理不尽と思われることをわが国は平然とやってきたのです。それに対する風刺だったのですね。詩をこんな風にも書けるのだと改めて思いました。言葉の力のひとつの見本だと思い直しています。
![]() (4月の部屋へ戻る)
(4月の部屋へ戻る)
![]()