| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.4.14(日)
家に帰り着いたのは午前6時でした。午前0時から歩き続けて6時間、さすがに疲れましたね。実は前日の日本詩人クラブ3賞贈呈式の後、あちこちで呑み過ぎて、帰りの電車賃が足りなくなったのです^_^;;;
お金が足りない!というのは新宿駅で気付きました。酔った勢いというのは怖いですね、まあいいか、行ける所まで行って、あとは歩くか、と決めてしまったのです。最寄の駅まで行って、嫁さんに来てもらうという手も考えましたけど、深夜では嫌な顔をされるのに決っています。日頃から自分の行動には責任を持て、と家族に言っていますから、とても「迎えに来て」なんて言えない。大口を叩くんじゃなかったなとしみじみ思いましたね。
まあ、中高年の登山やウォーキングが流行っている時勢でもありますし、ざっと計算して25キロ、歩けない距離ではありません。高校生の時に弟と二人で日帰りの富士登山をやったのが、多分最長の歩いた時間。あの時は15時間ぐらい歩いていますから、それに比べれば6時間なんて軽いものです、、、って、30年以上も前の体力で考えてしまいました。でも、思ったよりは楽に歩けましたよ。小田急線の伊勢原という駅から246号線を南下すると、小さな峠がひとつあるだけでほとんど平野ですからね。
得したな、とも思いました。意外と自由な時間だったのです。今日一日は予定が這入っていませんでしたから、時速4キロのゆったりした気分で歩きました。そうしたら、いろいろなことが考えられるのです。そういえば、こうやってゆっくり自分を考える時間がここのところ無かったなと思い至りました。思いもかけぬ時間をもらって、得をした気分になったのです。
買った本やいただいた本でバッグは重かったし、一張羅のスーツはちょっと歩き難かったし、暴走族には何度も遭遇しましたけど、久しぶりに明けていく空を見て清々しい気分で歩きました。酔いがだんだん醒めて、なんでオレ、こんなことをやってるんだろう、という疑問も時々頭をもち上げてきましたが、それは強引に捻じ伏せました^_^;
まあ、あまり経験したくはないことではありますけど、30年に一度ぐらいはいいか、、、って、30年後は80歳だなぁ。
| ○山口敦子氏著『昭和自叙伝 家出っ子』 |
 |
| 2002.3.10 東京都板橋区 待望社刊 1200円 |
日本詩人クラブ会員の著者の自叙伝です。1967年、24歳の折に書き上げていたものを上梓したそうです。17歳時、18歳時、そして23歳頃の3部に大きく分れています。内容のおもしろさもさることながら、うまいなと思ったのは構成です。家出をして東京に出てきた18歳のことから書き出されています。そしてなぜ家出に至ったか、17歳のときの描写に這入ります。そこで読者はすべてを納得することができます。最後は23歳頃のすべてを許して(許されて、にあらず)帰郷した折の同窓会で結ばれます。
自叙伝はだいたいが鼻持ちならないので好きではありませんが、この作品は違いました。己を抑えて、周囲の人たちを冷静に観察し、文学の域にまで高めていると言ったら過言でしょうか。ちょっと小説を勉強した人なら、おそらく長編小説にしてしまったでしょう。それだけの内容と時代背景の描写を持っています。幼いときから詩人になりたい、画家になりたいと思っていた著者の天性の文才を見る思いがしました。
秋田の古い体質の田舎から東京に出てきて、看護婦を経験し現在は保育園を経営するまでに成功した著者です。しかし故郷では高校を中退して飯炊女まで体験したという自伝は、著者を知る私には正直なところショックでした。かなり長いつき合いになりますけど、著者の外周のみを見ていた不明を恥じます。昭和30年代の日本を語る、歴史的な一冊とも思います。
| ○隔月刊誌『千年紀文学』37号 |
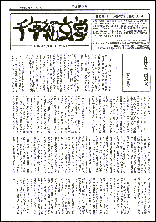 |
| 2002.3.31
東京都杉並区 皓星社内・千年紀文学の会発行 390円 |
ひとり旅/桜井さざえ
笹の葉に足を盗られながら獣道を登る
亡き母の自慢だった
日がな一日陽の射していた段々畑は
雑木林と竹薮に占領されて
木々の隙間からも海は見えなかった
祖父や父が石の一つ一つを積み上げた
段々畑の石垣の
崩れた石はそのまま放置され
畔の野仏のお顔も雨風に曝され石くれに
花挿しの徳利が割れずに土に埋もれて
梅は遥か高みに青い実をつけ
木下闇のなかに白い蜜柑の花が散る
人にも鳥にも見捨てられた甘夏の
水分のぬけた黄色 風に吹かれ
人魂のように木々の梢で揺れている
何を決めかねわたしは此処に来たのか
父を呼び母を呼ぶ
大声張り上げ泣いても誰にも聞こえない
死者たちに届くか わたしの声
不意に背後から鳥が飛び立つ
おそらく「ひとり旅」で故郷に帰ったときの作品だろうと思います。すでにご両親は亡く「亡き母の自慢だった/日がな一日陽の射していた段々畑は/雑木林と竹薮に占領されて」いる状態になっていたのでしょう。「花挿しの徳利が割れずに土に埋もれて」いるのも「人にも鳥にも見捨てられた甘夏」が「人魂のように木々の梢で揺れている」のも、作者の寂寥とともに読者に伝わってきます。
「何を決めかねわたしは此処に来たのか」という作者の思いは、私たちの中にもあるのかもしれません。故郷には縁薄かった私にも、時々40年以上も前の光景が立ち塞がってきます。作者の「ひとり旅」は、私たち一人一人の「ひとり旅」であるのかもしれません。
![]() (4月の部屋へ戻る)
(4月の部屋へ戻る)
![]()