| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.7.11(木)
台風一過、クソ暑い中を品川まで出張してきました。東京は35℃近くまでいったんじゃないでしょうか。でも、最悪の場合は台風が居直って出張できないケースもあり得たわけですから、暑いぐらいでクダを巻くようじゃしょうがないですね。出張の目的も達成できたし、ここは素直に喜びましょう。
帰社したのが15時。弊社の規定ではそのまま帰宅してもいいことになっていたんですけど、やっぱり会社に行っちゃいました。仕事第一なんで^_^;
まあ、それは冗談ですけど。先週、私のところに異動してきた後輩がちょっと心配だったんです。一応、上司に依頼はしてありましたが、この眼で仕事の状態を把握しておきたかったのです。きちんとやっていましたよ。異動したばかりで専門知識は無いけど、素直で前向きで、なかなかいい奴だと思います。39歳という年齢は社会的には決して若い方ではないんですが、一回り年配の私から見ればまだまだ若い。いい戦力に育ってほしい、そうするのが私の役目と思っています。
| ○詩誌『孔雀船』60号 |
 |
| 2002.7.10 東京都国分寺市 孔雀船詩社・望月苑巳氏発行 700円 |
詩が生まれた時間/藤田晴央
寺の境内には
向かい合わせに座るブランコがあった
幼稚園から小学校にかけての頃だったから
片側に詰めて三人はすわれた
一人乗りのブランコはどこにでもあったが
その汽車の座席のようなブランコは
どこにでもあるというものではなかった
だから人気だった
みんなでわぁわぁ言ってすわり
最後の一人が地面に立ってブランコを揺らし
だいぶ揺れたところで
ぱっと飛び乗って
真ん中に足を広げて立ち
吊り鉄棒に両手を大の字にしてつかまり
開いた足で調子をとりながらなお揺らす
だんだん揺れが激しくなると
きまって一人の子が
「止めてぇ!」と叫ぶ
そんな声をほかの子どもたちは聴いちゃあいない
ただもうきゃあきゃあ言っている
「止めてぇ!」と叫んだ子は
(つまり五歳か六歳くらいのわたしなのだが)
なんだかおちんちんのあたりがむずむずして気持ちが悪い
このまま大変なことに
たとえば死んでしまうとか
そんなことになってしまうのではという恐怖に襲われ
「止めてぇ!」と絶叫する
声よりも泣き出しそうなわたしの形相に気がついて
ようやくブランコのスピードが落とされ
わたしは一人だけブランコから降りる
ほかのこどもたちはまた揺れを激しくして
ブランコを漕ぎ出す
また次の日みんなで来るときには
同じように最初は笑顔でブランコに乗り
また途中でこわくなって降りてしまうのに
仲間はずれにされたことはない
ただ途中で降りたあとしばらくの間
わたしは一人きりだった
たいした時間ではなかったが
一人で所在なく
命からがらブランコから生還した興奮も一瞬のうちにさめて
一人きりであった
いいタイトルだなと思います。そして作者の「詩が生まれた時間」を納得してしまいます。確かに多くの詩人には「たいした時間ではなかったが」「一人きりであった」時間が原点であったろうなと想像できます。作者の原点に忠実な感覚には脱帽しますね。
女性には別の感覚があるのかもしれませんが、男としては「なんだかおちんちんのあたりがむずむずして気持ちが悪い」というフレーズも良く判ります。これも詩の原点なのかもしれません。作者の年齢は知りませんが、私にとっては50年近くも前の感覚を鮮明に呼び起こしてくれた作品でした。
| ○詩誌『RIVIERE』63号 |
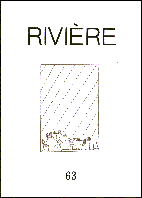 |
| 2002.7.15 大阪府堺市 横田英子氏発行 500円 |
蜜蜂-食虫記(5)/正岡洋夫
私の家業は養蜂業である
家訓には他の仕事には手を出すなとある
昔は一○○群は飼っていたらしいが
今はミカン畑に空の巣箱がたくさん並び
燻煙器も防護網も納屋に置いたままである
私はやむをえず家業を引き継いだのだが
残っていた群は雀蜂に襲われて死に絶え
入れ替えた群はダニにやられて死んだ
それでも生き残った仲間がいて
王座にまた女王蜂が選ばれて
せっせと子どもを産み始めた
働き蜂は蜜を集めに出かけるようになった
私が網をかぶって蜜を採っていると
初めの頃は蜜蜂はみな嫌な顔をしていたが
今では急かすように分離器の回りを飛び回っている
私は一日中巣箱の入口に立って蜜蜂を守っている
獰猛な雀蜂や足長蜂が襲ってくることがある
その時は一匹残らず頭から齧ってやる
敵のやってこないのどかな春には
朝早く働き蜂と一緒に飛び出して
喉いっぱいに花蜜を集めて帰ってくる
途中で無性に山に帰りたくなることがある
木にぶら下がった大きな巣を思い出し
時々背中に羽が生えている夢を見る
私の家系は在来種である
家訓には仲間の蜂を大切にせよとある
系図には時々蜂が生まれると書いてあるが
父も母も私が生まれてすぐに雀蜂にやられて死んだ
私は残念なことにまだ蜂ではないが
私の顔は毛深く目玉が大きく飛び出している
額のあたりに触角が少し生えていて
口には蜜を吸う管が伸びている
蜜蜂は家の中を雲のように飛び回っている
私はミカン畑の巣箱に住んでいる
大きな声では言えないのだが
私の二人の娘は蜂である
登場する職業が珍しいこともありますが、誰もが書けるわけではない貴重な作品だと思います。蜂の生態を理解し、蜂に同化する意識が無ければ書けないのではないでしょうか。「私」がだんだん「蜂」に変っていくところが特におもしろいですね。最終行の「大きな声では言えないのだが/私の二人の娘は蜂である」というフレーズは、作者の〝してやったり〟という笑みが見えそうです。
生物を見ることは人間を見ることなのかもしれません。作者の真意はそこにある、と言っては言い過ぎかもしれませんけど、そんなことまで考えさせられる作品だと思います。
![]() (7月の部屋へ戻る)
(7月の部屋へ戻る)
![]()