| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.11.10(土)
ひょんなことから同年代の詩人が集って呑もうじゃないか、という話になって池袋まで行ってきました。集ったのは私を含めて6名。ほとんどが50代前半の人ばかりです。詩人の世界というのは昔から老齢化が進んでいて、中心になるのは常に60代後半から70代前半の人たちです。そんな中で私たちはまだまだワカゾー。会社勤めをしていると、そろそろ定年を考える年代なんですけどね。
いつもは先輩方に敬意を表して、失礼のないように振舞っていますから、意外と疲れるのですね。そんなことを感じていたのは私ばかりでなかったようで、この日の集りとなりました。誰に気兼ねすることもなく、せいせいと呑みました。当然、詩の話になりましたけど、いつもならこんなことを言うと誰それにどう思われるか、なんて変な気を遣っていたんですが、それもなく、言いたいことを言い合えました。本当はそれでは駄目で、年齢に関係なく言いたいことを言えないといけないんですが、ちょっと現実と離れてしまいます。
詩人というのは最も権力から遠い存在であるはずなんですけど、詩人も人の子、権力志向の人がいるのも事実です。私たちが変に遠慮をして、言いたいことを言わずに来たことも原因しているかもしれません。私個人としてはそんなことを考えた呑み会でした。
| ○田川紀久雄氏著『続・詩語りの現場報告』 |
 |
| 2002.11.20 東京都足立区 漉林書房刊 1800円+税 |
田川紀久雄さんは詩の朗読(ご本人は詩語りと称しています)に真剣に取り組んでいる方です。ほんの短い時間ですが彼の朗読も聞いたことがあり、この夏はCDもいただいて堪能していました。彼の朗読論は詩誌『漉林』で何度か拝見しているのですが、今回まとまって拝読する機会を与えられ、いろいろ考えさせられました。この本のすべてを紹介するのは無理ですが、エスプリのような個所がありましたので、その全文を載せてみます。
詩の朗読は何処に根拠があるのか
詩を朗読する意味はどこにあるのだろうか。それはとりも直さず内在的爆発性のエネルギーを、その詩から感じ取るところから生まれてくる。
詩の意味をそのまま伝達するのなら、散文を朗読しているのと何ら代わりばえがない。素読は、詩を朗読することを拒否しているのではなかろうか。素読で詩を聞かされた場合、聞き手は多分苦痛を感じるに違いない。それは、あくまで意味のみに追随しているからである。意味だけなら、別に朗読する必要もない。
詩人は、なぜ朗読するのか。それは活字では味わうことのできない言葉(声)の源に帰還するための一つの試みを行いたいという衝動にかられるからではあるまいか。現代人は、ますます声の(肉声)力が弱まっている。声の発生は、自然にたいする恐怖感から生まれたものであろう。ものに対しての怯え声・叫び声・唸り声・泣き声・笑い声が、言葉になる以前あったはずである。生き物である以上、そのような声を忘れ去ることは、どんなに文明が発達しても、できないものである。そして、言葉(伝達)が生まれても、言葉の奥には、そのような感情の声が潜んでいる。活字だけにたよっていては、人としての感性を失っていかざるをえない。声の温もりを失ったところには、ヒトとヒトの繋がりも失われてゆくことだろう。
いま現代詩の、生命力が失われているのも、活字信仰が強いからである。生き物としての声の発生地点を忘れているからである。活字にならない以前の声の生命体を呼び起こすことが大切なのではあるまいか。そして、その声を取り戻すことの中で、詩を朗読(詩語り)が一番やりやすいのではなかろうか。詩には、つねに言葉以前の声が、要求されているからである。散文と違って、それほど意味性が重要ではない。あくまで、内在的エネルギーが大切である。そこに、詩の核がある。
詩人の中には、詩の朗読を否定する人がいる。そのような人たちは、殆ど活字信仰者である。声と活字は、別な問題である。活字は、あくまで社会性を求めた伝達のための記号でしかない。声そのものは、声を発した時から、個人の内的存在性のエネルギーの発露である。詩を朗読するとき、活字を読みながら同じに言葉にならない声も発していく。それは、言葉の源に還える旅の始まりでもある。
今、活字→言葉→声に遡ることによって、本当の詩の生命いのちを取り戻すことが出来るのでなかろうかと思っている。(一九九九年十月十二日)
田川さんの思想を端的に示した文章だと思います。もっと具体的で私たちに身近な、詩人のイベントでの朗読なども鋭い批判に晒されていますが、詳細は本書を読んでいただければと思います。私も基本的には練習を積まない詩人の自作詩朗読は嫌いです。他人様に無礼になるような朗読はやりたくないと思っています。
なお、紹介した文章のうち、明かな脱字は訂正してあることをお断りしておきます。
| ○詩と評論・隔月刊誌『漉林』110号 |
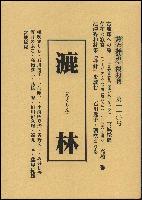 |
| 2002.12.1 東京都足立区 漉林書房・田川紀久雄氏発行 800円+税 |
妹/香野広一
二人は まだ幼なかった
妹は三歳 ぼくが六歳
父は海軍兵に招集されて
出征して
留守であった
里山には
疫痢が蔓延して
隔離する所がなくなっていた
医者と看護婦も居なく
あしたの食ベ物もないのに
死者だけが
日増しに増えていった
妹とぼくは
外にある便所に
競って走った
憔悴した妹は
よろけるようにして
一日に何十回も
かけこんだ
枢の作り手のないまま
妹は そっと
墓の片隅に
土葬された
だれにも見送られることもなく
冷たい 土の闇に
ぼくだけが
あれから何十年間も
生存(ながら)えている
奇跡のようなぼくに
妹が そっと
寄り添っているのかも知れない
作者は一見すると大人しそうな、やさしい方です。でも、ある種の芯の強さが感じられて、それはどこから来るのかなと思っていましたが、やっとそれを知ることが出来た思いです。もちろん詩作品ですから、実生活と切り離して考えることが必要でしょう。しかし、詩人には詩を書かざるを得ない理由があるのも確かです。その根本的な理由を見た、と思いました。
国は今、再び同じ過ちに向って進んでいるように思えてなりません。「枢の作り手のないまま/妹は そっと/墓の片隅に/土葬された」状態が再び来るのではないか。作者の個の問題が、個の責任ではないことに腹立たちさを覚えます。そんなことを考えさせられた作品です。
| ○詩誌『禾』4号 |
 |
| 2002.7.1 宮崎県東諸郡高岡町 本多企画・本多寿氏発行 500円 |
五月闇/中島めい子
――胃も腸も日々固くなっていく
くずれそうな細い肩のその人は
不安な眼差しでわたしを見つめる
――そのうち何もかも固くなって……
わたしは石になるのでしようか
白い蟻のような感性の羽根をふるわせ坐っている人よ
あなたのまわりは
固まった眼 固まった言葉の住人
このわたしも 日々経験の節をなぞりながら
精神のペンダコに苦しんでいる
――固まったものは溶けるのですか
その人のおびえた眼に一瞬 光が走る
――溶かすには熱い火がいるのですか
あなたの問いの前で
さらに重い問いをかさねながら
わたしは黙る
気がつけば 五月
問いつづけた人は もういない
野アザミ シロツメグサ
ビヨウヤナギの傍に
その人の言葉をさがす
五月闇の中で
死者は新しく孵化する
明日への導火線をかかえて
最終連がよく効いている作品だと思います。「あなた」と「五月闇」の関係もうまいですね。「あなた」の怯えや不安が読者にも伝わってくる作品です。「胃も腸も日々固くなっていく」という具体性が、ある凄さを伴って伝わってきます。
それに対する「わたし」は「日々経験の節をなぞりながら/精神のペンダコに苦しんでいる」と云う。これもうまい表現で、人間の精神の、底知れない深さを知らされた思いです。
![]() (11月の部屋へ戻る)
(11月の部屋へ戻る)
![]()