| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 「クモガクレ」Calumia godeffroyi カワアナゴ科 |
2002.12.13(金)
午後から東京本社に出張しました。業務依託会社のうちの1社との定例技術検討会です。この会社は技術的にも高いレベルにありますから、ほとんど問題を起していません。本当は定例会など必要ないので、2年ほど止めたことがあります。しかし、それはそれでお互いの意思疎通が希薄になるという面が判って、今年から復活させた経緯があります。お互い人間通し、たまには顔を見せ合わないと駄目、ということですね。
そんな訳ですから、会議も和気藹々としてなごやかなものでした。話はどんどん前向きになって、会議をやっていても楽しいものでした。年末ということもあって、帰りは弊社が招待して忘年会をやりました。招待というほどの大袈裟なものじゃありませんけど、まあ、気持だけということで…。仕事の上で酒を呑むのはあまり好きじゃないんですけど、今夜は良かったです。八重洲のイタメシ屋さんでしたけど、洒落ていて、いい雰囲気でした。
| ○詩誌『木偶』52号 |
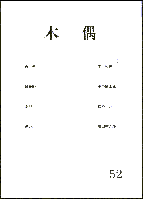 |
| 2002.12.10 東京都小金井市 木偶の会・増田幸太郎氏発行 300円 |
その次の夜、病状は更に進み、もう歩行は困難となる
仄かに燃える命の行く末が見えて来た
死への階段は己の力で降りて行く
わたしはその声を聞いていた
死を和らげる術はなく
母は胸を撫ぜ下ろして呼吸を和らげ
お互いを励ましながら懸命に刹那を繋いでいた
急を告げていた
全身で払いのける強力な痰を
残る力で抵抗し反応するけれど
次第に消耗し燃焼した力に尚も寄せる潮の痰の攻勢
阻もうとするが尽きてしまう
何もしてやれない朝の異常な長さである
時間はいつもと同じように刻んでいた
悶絶の声がする
ああ惨いことよ 傷ましいことよ
死に飲み込まれる悲惨なかたちである
全身の力が抜けていく
安らかな平静が嘘のように訪れた
それが死である、偉大なる帰属である
生命の終焉であった
わたしはその声を聞いていた
その慌ただしい緊張のあと、わたしはすべてを忘失した
微笑みと血の気を失った皮膚
限りなく生きるために渾身の力を使い果たし
生き物を奪われた骸が長々と横になっている
青白く豆腐のように涼しい顔がある
その容姿は沈黙し凪の海のように平静である
わたしはまだ暖かさの保った姉を抱き寄せて泣いていた
点火した火を見届けて男衆は帰って行った
大きな鉄の板に用意された木々が敷かれていた
その上に棺箱を置き丸太で囲み男は急いで石油を振りかけ火をつけた
野辺の送りを町外れで多くの人と別れて
わたしは男衆の担ぐ棺の後に従って墓地まで来た
雪道が続いていた
すでに朝から除雪をして焼き場までの道は切り開かれていた
わたしは独り火炎に覆われた棺を見つめながら
燻り続ける煙の中に鉄の棒を使って空気を入れると
火は勢いを増して木棺を舐めるように勢力を盛り返す
すると姉は足を伸ばして立ち上がってくる
熱は硬直した筋肉を和らげて姉を呼ぶのである
結んだ手がほどけて炎の中に現れる
突然、頭に火が這う
頭蓋骨がパックリと蓋を開ける
すると忽ち頭の中は騒然と火の海になる
飛び散る火の華に驚いていると
青い闇がほどけ、雪崩のように砕ける
奇妙に競合するセンコ花火のはじける音
閃光が鋭く散らばる
おお 神秘の狼煙 奇怪なる造形よ
黄が飛ぶ、青が散る
煩悩が燃える
金が銀の光に押し出されて交わる
緑が瞬くまに入り乱れて噴出する
魂の最後のかたちが炸裂する
わたしはこの異様な火に
不可思議な終焉のかたちを見たのである
風か吹いて来た
小雪が落ちて来た
火焔は勢いを増して姉の緩んだ身体を攻めている
わたしは火柱と向かい合っていた
夕暮れが近ずいていた
小高い丘に幾つもの石柱が見守っている
山麓の原始林を切り開いた開拓民の墓である
望郷の想を最後まで持ち続けて彼らは去って行った
わたしは底冷えのする風に吹かれて火焔の落着くのを見届けていた
増田幸太郎氏「遠い声」部分
非常に長い詩で、紹介したのは全体の4分の1に過ぎません。1946年に28歳で亡くなった姉上の臨終と火葬の部分だけを転載しました。この前後も非常に感動的なのですが、載せ切れませんので割愛しました。
増田さんの作品は非常に長いことで有名です。この作品は25行詰めで12頁もありました。今回の作品を拝読してつくづく感じたのですが、やはり長いには長いなりの理由があるということです。ドラマがあって、それをリズムで追っていくと長くなって当然だろうと思います。それが圧倒的な物量として読み手に迫ってきます。そして次々と行を追ってしまうのです。それだけの迫力を紹介した部分だけでも納得してもらえると思います。
それにしても1946年頃の火葬というものは凄まじいものだと思います。ある意味では歴史の証言であるようにも感じます。それを冷静に見ている少年(当時は少年だったと記述されています)の、奥深い哀しみが伝わってくる作品です。増田詩の真髄を見せてもらった気がします。
| ○古賀博文氏詩集『人魚のくる町』 |
 |
| 2002.12.31 大阪府豊能郡能勢町 詩画工房刊 2000円+税 |
湾岸線(A町へ)
レールは夏の炎天にあおられて
周囲の時空とともにゆがみはじめていた
私は「太古」というおおきな蝉が
駅の改札口でさかんになくのを聞いた
地中からはいでてくる一両編成の無人列車
私はまばらな時刻表の余白によばれていった
犬の尾のかたちをした砂嘴(さし)のうえを
上気し、うねうねと蛇行していく二本の感情線
暖流の湾曲がはきよせた摺曲地層には
南方の異形な神々の遺留品などがうまっており
ここは荘厳なノスタルジアの原野
おびただしい遺跡群が軌道の左右に散在し
「弥生」「貝塚」「竜ノ巣」「土器原」「窟」
いちいち停車していく駅名が
既視感の吃水をあやうく波だたせた
終点A町へおりたつ
にぎわったであろう朝市はすでにとじられ
しろい海鳥たちが朱色にはねをそめながら
放置された魚の頭部をうばいあっている
(正餐におくれてきたものたち……)
魚の肉汁で充血した水面
帰港した漁船が
その粘液のユリカゴのなかにつなぎとめられ
日没までのわずかな仮眠をむさぼっている
犬がいっぴき
どこかで吠えつづけている
つんとはなをつく港のワキガ
《潮の香》とは芳香のたぐいなどではなく
雑多な生物の死臭にほかならない
それでもひとが海にひかれるのはなぜだろう
それは海にくれば会えないひとに会えるからだ
蒸発した漁夫 夭折した漁夫
もえた漁夫 おぼれた漁夫
うまれなかった漁夫たち
(漁夫の姓をもつ私の一族)
死者が地形をかりて生者を手まねきする
私はこれからだれかと対面しようとしている
茫々たるこのいまわの地で
巻頭作品です。詩集を最後まで拝見して、結局この作品に戻ってきてしまいました。この作品が頭から離れずに、また戻ってきた、と言った方が正確かもしれません。第3連の「つんとはなをつく港のワキガ/《潮の香》とは芳香のたぐいなどではなく/雑多な生物の死臭にほかならない」というフレーズが作品の根底にあるような気がしてならないのです。
一般的に「《潮の香》とは芳香のたぐい」でしょうし、私個人もそう思ってきました。それが「雑多な生物の死臭にほかならない」と言うのですから、頭をガーンと殴られた気がしました。確かにその通りなんですね。もちろん潮そのものの匂いもありますが、やはり魚や貝の死臭もある。それを「港のワキガ」と表現するのは見事です。固定観念を打ち砕かれた思いをしました。
この詩集は、そういう私の固定観念を次々とブチ壊していくものでした。著者は、時に過激とも思える評論でも著名なのですが、その源泉を見たように思います。評論と作品とが一致した詩集と言えましょう。タイトルポエムの「人魚のくる町」、「黒い鳥」「炎熱隧道」など、コリ固まった頭には随分と刺激的な作品です。
| ○原田道子氏詩集 『うふじゅふ ゆらぎのbeing』 |
 |
| 2002.12.10 東京都千代田区 鮫の会発行 2500円 |
キララの家
いくたびのぞいてもつきないイクサの森
しろつめ草を十字にさげた首のない子の声がする
膝を折る地に手を置く指をはわせながら
文字や記号に繋がっているのはいいことで
そういえば
あの日のあの時あのゲリラのように
核が塵になる しのびよる
そんな気もした。が
有史以前のか。ぜ。はいつものようにくぐもって
たとえば危険を報らせるあるいは企み。のように
いつまでもおとずれない死を転写する
ゆがんだ森がひときわ光っている
かあさんを演じるひこばえの炎に
もはやきわどい貌かたちのまま
切り立った崖のうえでうつむいていたいよ
昏れようとする半狂乱の千年紀に
いこう。キララの家に
ひふみゆらゆら。ひふみゆらゆらひふみゆらゆら
原田さんの詩は非常に難しくて、どこまで作者の意図に迫れるか判らなくて、いつも自分の限界を感じてしまいます。でも、言わんとしていることは何となく判りそうな気がする、というのが正直なところです。ポイントを押えるのは言葉だろうと思っています。例えば「キララ」は広辞苑によると雲母(うんも)と煌ら(きらめくさま)の二通りありますが、主は前者、後者の意味も内在すると思います。「イクサ」は戦で良いでしょうがカタカナであることに注意が必要でしょう。どう注意するかは、うまく説明できないのですが…。「しろつめ草」は〝詰め〟が「首のない」に掛かってくると思います。「か。ぜ。」にも要注意。風ではありません。「か。ぜ。」は風のように一気に流れません。「か」で止まり、再び「ぜ」で流れ、そして止まる。そのために「。」があるのだと思います。
そんなふうに一字一字に注意して読んでいって、最後に、ああ、戦争や平和のことを語っているのだなと納得すれば良いのでしょう。最終連の「いこう。キララの家に/ひふみゆらゆら。ひふみゆらゆらひふみゆらゆら」は希望ととるか諦めととるかは難しいところですが、「文字や記号に繋がっているのはいいことで」というフレーズを強引に引き寄せて考えると、諦めではないと思いたいですね。「キララの家」を言葉通りに採ると、逃避という線も考えられます。
「森」も気になる言葉です。「ひこばえ」と合わせて考えると、人間社会そのものととって良いでしょう。「かあさんを演じるひこばえ」は大人、しかも母性を演じる蘖(伐った草木の根株から出た芽)ととると、何やら底知れぬ力を感じます。
…… オレって、本当に頭が悪いんだナ^_^;
| ○北野一子氏詩集『蛇の目傘』 |
 |
| 2002.12.15 大阪市北区 編集工房ノア刊 2000円+税 |
蛇の目傘
そこまで母が迎えにきた
うすやみの夢をみた
いまはない 深川の幼稚園の
木肌の幅広い階段に腰かけて
当たり前のように 待っていた顔でなく
不意をつかれて わたしは後ずさりした
そう 戦後五十余年母のいない暮らしだったから
じっと見下ろす母は
もう身構えるな
丈夫な身体で生んであげたでしょう
安心なさい と目で言った
映画館と芝居小屋に挟まれた
地続きの家で 母は忙(せわ)しなく働いていて
わたしは暗闇の映画館へ走り 地べたに座り
夕方 母の迎えの手を待っていた
今、白い顔の母は傘をさしている
背中に 赤ん坊だった妹の顔はなく
ただ わたしの雨具を持って立っている
もう嘆くことも 苦しむこともなく
手を含わせることもなく
すべてを亡母にまかせて
彼岸の川を渡れば良い
そんなことが すうっーと悟れた
詩集のタイトルポエムで、一番最後に置かれていました。「背中に 赤ん坊だった妹の顔はなく」というフレーズは説明が必要でしょう。「こと有りて」という作品には「四人の子を生み 三十二歳の若かった母は/東京大空襲の無差別爆撃でそのまま逝った」というフレーズがあります。また「負ぶい紐」という作品に「わたしの街の大空襲の夜/母の負ぶい紐の背中には 二歳の妹がいて/四歳の妹の手を繋いでいた筈の 母達三人/仲良く重なるように/土に還ったとずっと思い込んでいた/(だれも見たものはいない)」というフレーズがあります。そこから「妹の顔はなく」という意味を連想しなければなりません。
それらの困難を乗り越えた後の現在、やっと「すべてを亡母にまかせて/彼岸の川を渡れば良い/そんなことが すうっーと悟れた」状態になったのだと思います。そういう時代の証言としても重要な詩集と言えましょう。この作品をタイトルポエムとし、詩集の最後に据えたことは正解だったと思います。「Ⅰ」は別として、「Ⅱ」は作品群はこの一作に収斂しており、著者の意図が明確に伝わって来たと思います。
| ○藤倉明氏詩集『街の灯の中で』 大宮詩人会叢書第四期(26) |
 |
| 2002.11.20埼 玉県さいたま市 大宮詩人会叢書刊行会発行 1300円 |
つばき
冬中ひそかに育んできた愛しみを
つぼみの先端に ぽつんと
紅色ににじませてから数日後
考えあぐねていた問題を解いたかのように
一輪 二輪と咲き出した
それでも きのう吹いた南風に
欺かれたことを揃って恥じているのか
青く腫れた葉と葉の陰に身を引いて
幾重にも赤面を重ねた花びらの奥に
秘めた寡黙なほほえみとエロス
紺青に晴れ上がった空を
ふり仰ぐこともせず
首を深く垂れ 地面に向かって
おのれの鮮やかすぎる発情を恥じ
世間の指弾に耐えつづけていた
厚い雲が空の片隅から次つぎに湧き出て
葬列のように流れていった日の
風もやみ 物音の絶えた昼下がり
花たちは相ついで詫言のような声を残して
風景の外に脱落していった
うちの庭にも椿が一本ありまして、でも「考えあぐねていた問題を解いたかのように/一輪 二輪と咲き出した」なんて風に見たことがありませんでしたので、思わず見に行ってしまいました(正直なところ、椿があることも忘れていて、確認に行ったのです)。まだ小さな蕾でしたけど、あぁそうか、そんな風にして咲くのかと納得してしまいました。うちの椿は何も考えずにボーッと咲くのかもしれませんけどね、家主に似て…。
第2連、3連、最終連とも見事だと思います。こんな風に観察された「つばき」も本望でしょうね。たとえ最後は「風景の外に脱落していった」としても。樹木を観察する眼を教えてもらった作品です。
自分のことばかりに引き寄せてごめんなさい。「足柄の御坂に立して」という作品の第1連は次のようになっていました。
--------------------
<その日 私たちは小田急線を新松田駅で下り バスを乗り継いで関本を経て地蔵堂に着き そこから歩いて足柄峠を目指した。地蔵堂から峠へは右手に椀を伏せたような山容の矢倉岳を見て 九十九折の舗装道路を縫いながら登る。奈良時代に東国の防人たちが くにを離れる悲しみに涙しながら越えた古東海道足柄道。>
--------------------
この「矢倉岳」というのが私の家の裏山になります。「関本」は通勤で毎日通る駅、「地蔵堂」は隣の自治会です。私の地域の内山という所と矢倉沢・「地蔵堂」は北足柄地区と呼ばれ、何かるといつも一緒に行動する関係です。
まあ、そんなことは作品の上ではどうでもいいことなんですが、自分の地域が作品に採り上げられるとうれしくなるもんですね。この作品も格調高く、万葉集を深く読み込まれていることがよく判りました。
![]() (12月の部屋へ戻る)
(12月の部屋へ戻る)
![]()