きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.6.18(水)
明日は山形に出張するというので一日中大忙しでした。業務委託会社の工場監査が年に一度義務付けられていて、私としては担当になって初めてのことですから、過去の書類を引っ張り出して、新たに加えるものは加えて、一日中書類整備で終ったようなものです。でもまあ、納得のいくものになりましたから大丈夫でしょう。
他所様の工場を監査するなんて私の性に会わないことですが、仕事ですから文句も言えませんね。今回は女性も加わって5人の部隊で乗り込みます。無事に終ることを祈るのみです。
| |
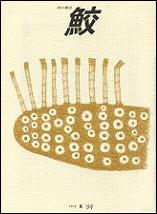 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.10 |
| 東京都千代田区 |
| <鮫の会>芳賀章内氏
発行 |
| 500円 |
| |
かえりが怖い 大河原
厳
名刺入れを背広のポケットにつっこんで
さて! と言うだけで
もうぼくは名刺の人物になりすましている。
これは長い間の修練で身につけた変身術だから ほとんど完璧にち
かい化け方である。
名刺の肩書きにふさわしい位置に ぼくの机と椅子があり つみあ
げられた書類が ぼくのサインをまっているかぎり 化けの皮が剥
がれてしまうようなことはない。
もうぼくは肩書きそのものだから 肩書きがひとに口をきき 肩書
きが字を書き 肩書きがメシを食って煙草をすっている。
もう誰も このぼくを疑わない。
名刺にある肩書きの背後の死角にかくれて
さて! に耳を立てると
ひとりだけ この完璧なメクモルフォーゼの一部始終に ぼくの完
璧なインチキ性を見ていたやつがいる。
やつは優しい そやつは頼りになる。
ぼくが絶体絶命の瀬戸際に立ったとき ぼくの(かえりが怖い)と
いう叫びを聞きとってくれるのは そやつだけだ。
名刺入れを机の引き出しにもどしても 肩書きのないぼくに化けか
えるのは困難をきわめる。進退窮まったぼくが もとのぼくに化け
かえりたくて夢のなかを輾転反側する。
そやつだけが(この道とおりゃんせ)と唄ってくれる。
(未刊詩集『自画像Ⅱ』より)
サラリーマンの哀惜に満ちた作品だと思います。「肩書きがひとに口をきき 肩書/きが字を書き 肩書きがメシを食って煙草をすっている」というのはその通りです。会社にとっても社員にとっても、一般的な社会も必要としているのは「肩書き」に過ぎません。肩書きの下に刷り込まれた個人名は次の会ったときに変わっていても、必要な肩書きの入った名刺を差し出されればそれで会社通しの話は済んでしまいます。相手が変わっても肩書きとおりの仕事をしてくれる会社が良い会社というわけですね。
それもあるけど、この作品の妙は「かえり」にあると思います。〝帰り〟の意味もあるし「化けかえり」もおもしろく絡んでいます。どれが本当の自分なのか、退職したらやっと判ることなのかもしれませんね。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.15 |
| 千葉市花見川区 |
| 中谷順子氏 発行 |
| 非売品 |
| |
落日 大籠康敬
葉を落とした梢に
柿の実ひとつ
燃える灯火のようにきらめいている
ススキの穂並が金色に光り
雲ひとつなく澄みわたったスミレ色の空の静寂
虫の音も絶えてしまい
川の畔に
日ごとに深まってゆく晩秋の気配
かさこそと落ち葉を踏んで
妻と私はいつもの散歩道を歩いてゆく
日は短くなり
二人の影は長々と伸び
かけ足で後ろから追いすがってくる夕暮れ
心せかれながらも
帰路
みごとな落日に立ち止まってしまう
大きな木の下で
妻と私は真っ赤な夕日に照らされている
空も水も雲も朱に染まって
樹々は黒い影となり
僕らも黒い影となり
ひと時
晩秋の空の彼方に鳴りひびく落日の荘厳ミサに
二人は声もなく聞き入っていた
日本詩人クラブの会員でもあった大籠康敬(おおこもり
やすたか)さんが亡くなったのは3月のことでした。今号ではその大籠さんの追悼が組まれていました。紹介した作品は最後の個人詩誌『水脈』に載っていた作品だそうです。おそらく絶筆に近いものかもしれません。そう思って拝読するせいか、何やらご自分の死を感じていたようにも受け取れます。写真家でもあった氏の、見事に映像的に描いた作品とも言えましょう。ご冥福をお祈りいたします。
| |
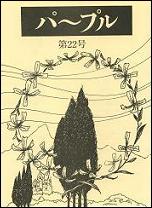 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.7.16 |
| 川崎市宮前区 |
| パープルの会・高村昌憲氏
発行 |
| 500円 |
| |
家族旅行 高村昌憲
梅の花から桜の花へ
季節の色が少し変わる頃
家族の距離を縮める旅へ
伊豆の海と山並みは同じ色
一人ひとりが少し無理をして
家族が変わろうとしていたから
変わっていくことへの勇気として
変わらない風景を見たかったから
「変わっていくことへの勇気として/変わらない風景を見たかった」というフレーズは素晴らしいですね。内容はそんな陽気なものではないんですが、この感覚があればきっと「家族の距離」は縮まると思うのです。そういうことを行間に感じさせる作品です。
家族というのはいつもある種の危うさを持っているものかもしれません。私自身の親たち、私の離婚経験などを考えるとより強くそう思います。それでもやはり、あるいはそれだからこそ「一人ひとりが少し無理を」することが必要なのかもしれませんね、「変わらない風景」を見習って。高村詩としては珍しく家族を扱った作品です。
 (6月の部屋へ戻る)
(6月の部屋へ戻る)



![]() (6月の部屋へ戻る)
(6月の部屋へ戻る)![]()