きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.6.23(月)
日本ペンクラブの電子文藝館委員会が東京・日本橋兜町の会館で開催され、午後から休暇をとって出掛けてきました。
討議の中で縦組み表示についての考え方が出てきましたから、ここに掲載しておきます。
ご承知のようにこのHPも日本ペンクラブのHPも横組みで表示しています。ところが日本語の文芸作品というのは圧倒的に縦組みなんですね。それがHP上では横組みになることに違和感を覚える人がかなりいます。今回もある詩人の遺族から作品を電子文藝館に載せてもいいという許可をもらったのですが、その前提条件が〝縦組みであること〟となっていました。以前からこの横組みについては生存している作家・詩人からも苦情が寄せられています。電子文藝館が発足する以前の電子メディア委員会の時代から統一した見解を持っていたのですが、今回改めて秦恒平委員長が書面化していますので転載します。遺族との間に入ってくれた人への回答文ですので、そこは勘案してお読みください。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
秦自身は、作品をすべて縦組みで書いて創って世に出してきましたが、機械の時代に入ってからは、横組みで書いて発信してもいます。
縦書きでしか書けないというのは「書き手」の意思と手法であり、それは書き手の自由です。一方読み手は、縦組みで読みたければそのように用意し、好きに読む。横組みでも読める人は、そのまま読む。それは「読み手」の自由です。「書き手」が自分の「縦書き」に拘るのと、読者に「縦組みで読ませたい」と拘るのとの間には、微妙な、質と立場の差があります。
「書き手」は書いた作品への自身のこだわりを、「読み手」に強いることは無理な相談です。読書行為は「批評」と同じなのです。読み手の批評を束縛できる書き手はいない。現に手書き原稿を、時には毛筆の字を、大勢が活字で読んできたのです。紫式部は想像もできないでしょう。本にも、大判も文庫本もあり、必ずしもそれは書き手が指定していない。
読みよいように「読者」に読んで下さいというのが、今日の「在りよう」ではないか。「書き手」が読者に「読み方や読まれ方」を強いるのは、ひいては、寝て読むな、正座で読めとか、電車の中で読むな、机の前で読めなどと言うのと似たり寄たりの「考え違い」ではなかろうかと、思っています。
詩や小説は「縦書き」というきまりなどなく、西洋では、当然横書き。横組みで読んだから値打ちの下がる作品なんて無いと、わたしは経験的に考えています。それは「慣れ」の問題でしかない。作風の歴史には、時代の慣れ要素が絡みます。そんな慣れの差を貫通して行く作品が、力ある古典への道を歩んで行く。
電子文藝館では、技術的経済的に簡単にそれが可能ならともかく、「縦・横」展示の「混在」は避けたい気がします。「読者に任せていい」と思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
私たちも最初は縦組みにできないかを考えてきました。もちろんPDFも視野に入れていました。しかし最終的には横書きに落ち着いたのです。技術的に難しいことと、テキストで提供すれば読者側が勝手に縦組みにできることが判ったからです。その上でさらに秦委員長の回答文にもありますように書き手が読者に縦書きを強いることは間違いなのではないかと思うようになってきました。作品を提供する側は、現在の器械で最も汎用性のある形で提供する、読者はそれを自分の好きな形に置き換えて楽しむ、それが電子時代の作品のあり方なのだろうと思います。
| |
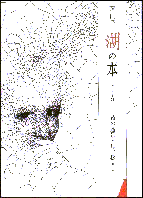 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.19 |
| 東京都西東京市 |
| 「湖(うみ)」の本版元
発行 |
| 1900円 |
| |
上述の秦委員長のエッセイ集です。総題に「繪とせとら論叢」とあり、絵、特に日本画についてのエッセイが集められています。
「猿の遠景―伝毛松『猿図』のことから」は、「NHKセミナー」(1990年11月号~1991年2月号)に初出したもののようで、東京国立博物館の重要文化財・中国南宋時代の『猿図』についての論考で、現天皇の〝日本猿ですね〟という発言に、なぜ宋画に日本猿が描かれているのか、日本猿を宋に送って中国人に描いてもらったものか、と学会が賑やかになるという面白いものです。
「母の松園」は1998年の没後50年記念誌「上松松園展」に寄稿したもののようです。この女流画家は美人画の大家として有名ですが、1935年に描かれた「天保歌妓」は18世紀末から19世紀初頭に描かれた祇園井得という画家の「美人図」が下敷きになっているのではないか、という推理小説にも劣らない面白みがあります。両方の絵の間に、1910年頃に松園が描いた「芸妓」という絵があり、この三作を並べると、その説が納得でき、絵の観方の面白みまで伝わってきました。
「球の面に繪が描けるか」は、平面を基本とする絵画に対する挑発的な論です。意外にも完全な球体に描かれた絵というのは無いのですね。理想としては何の支えもなく空間に浮いた球に絵を描いてみよ、絵描きは誰もやっていないではないか、という秦さんの挑発は実に愉快です。そういう新しさに絵描きは挑戦してみろ、という発言は、本当に絵を愛する人だからこそ出てくる言葉ではないかと思います。
最後に載せられている「繪のまえで―『みる』と『わかる』と―」は、1985年旧山種美術館で開催された「近代日本画の精華」展特別講演の記録ですが、これも非常に参考になるエッセイです。絵をみて、わかる・わからないということを言いますが、それを具体的に分析していて、納得させられます。実は絵に限らず文芸、音楽の分野でもわかる・わからないということは起きるのですが、基本的には絵の鑑賞と同じだという論は、モノ書きの端くれとしては一度きちんと考えてみる必要を感じました。
最後の最後、あとがきにあたる「私語の刻」では、わが電子文藝館も現状も報告。至れり尽くせりの一冊です。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.20 |
| 大阪府豊能郡能勢町 |
| 詩画工房・志賀英夫氏
発行 |
| 600円 |
| |
炎昼 中井ひさ子
小さな日傘をさして
二人はどこまで歩いていくのですか
精いっぱいに鳴く
蝉の声にも耳をかさず
奔放に咲く
ひまわりにも目をくれず
じっとりと汗をかきながら
「少し木影で休んだら」
と 声をかけたら
二人はだまって首を振った
何気なく読み過ごして、フッに何かが気になりました。何だろう?
「二人」という言葉に引っ掛かったんですね。二人? 二人って、誰?
二人とも「小さな日傘をさして」いるように受け止められるから女性同士かもしれません。別に男が日傘を差して悪いということはないけど、「小さな」では似合わないでしょう。ここはやはり女性の二人連れととった方が良さそうです。
その「二人はどこまで歩いていくのですか」? なぜ「二人はだまって首を振った」のですか? おそらくそのまま歩き続けて視界から消えたのでしょう。まるでかげろうのように…。そう謂えば「炎昼」というタイトルも奇妙ですね。辞書には載っていないようです。作者の造語のようですが、実に見事にハマッています。
「炎昼」の中をかげろう(陽炎)のように視界から消えていく二人、「じっとりと汗をか」くのは読者の方かもしれません…。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.18 |
| 大阪府豊能郡能勢町 |
| 詩画工房刊 |
| 1600円+税 |
| |
きかいに つようて
げんきが ようて
スピードずきな おんなの子やで
うちのゆめは パイロットや
ジャンボジェット機(き) うごかしたいねん
おんなの子かて やれるねん
やったら なんでも やれるねん
(二連略)
ちからが つようて
どきょうが ようて
スリルのすきな おんなの子やで
うちのゆめは レンジャーや
災害(さいがい)おきたら たすけにいくねん
おんなの子かて やれるねん
そやけど せんそう いややねん
へいたいさんには ならへんねん
大阪弁の童謡集『ほんまにほんま』(1980)、『大阪ことばあそびうた』(1990)などで知られる著者の方言詩、ことば遊びうたの論考集です。副題に「ことば遊びを中心に」とありました。紹介した作品は『ほんまにほんま』に収められている島田陽子氏自身による大阪弁による詩で、「おんなの子のマーチ」という題だそうです。この作品について、続けて次のように述べています。
これは敗戦を十六歳で迎えた昭和ヒトケタ世代の女の思いである。童謡とい
う形に託した詩であり、自分を含めた女たちへの応援歌といえる。このような
内なる少女の本音を表出するには大阪弁でなくてはならなかったし、それによ
って、東京生まれながら、十一歳からの大阪人である私は解放されたのである。
大阪弁のまるい言い回しの魅力と「そやけど せんそう いややねん/へいたいさんには ならへんねん」という戦争体験者の重い言葉が備わって、読者の感動を深めていると思います。20年も前に書かれた作品ですが、ようやく新幹線の運転士に女性が登場しましたけど、まだまだ「ジャンボジェット機」の「パイロット」は出現していないようです。でもいずれ出てくるのでしょうね。
ここでは大阪弁の作品しか紹介できませんでしたが、著者が教えている大学の学生による方言詩、谷川俊太郎、木島始、坂田寛夫などの回文を始めととすることば遊び詩などがたくさん出てきます。それらを楽しみながら方言とは何かを考える必要があるでしょう。それは結局、日本語とは何かを考えることなのだと読者は気づきます。言葉のおもしろ味は文化の豊かさ、そんな思いを強くした著書です。
 (6月の部屋へ戻る)
(6月の部屋へ戻る)



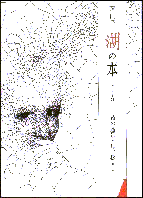
![]() (6月の部屋へ戻る)
(6月の部屋へ戻る)![]()