きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.7.2(水)
定時後に職場のキックベースボール大会というのが開かれて、参加してきました。野球やソフトボールのルールで、ボールはサッカーボールです。ピッチャーが投げたボールをバッター(?)は足で蹴るというものですけど、やったことある人、多いかもしれませんね。4チーム中3位という成績でしたけど、疲れましたね。普段、運動なんてやってませんからね。
優勝したのは製造課3交替勤務の職場です。選手は平均20代後半ですかね、若い者には負けます(^^;
他のチームは40代ばっかりでしょうか、トシの割には頑張ったと言えましょう。たまには運動もいいもんですけど、やっぱり筋肉痛になってしまいました。
| |
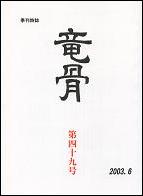 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.25 |
| 東京都福生市 |
| 竜骨の会・村上泰三氏他
発行 |
| 600円 |
| |
春 村上泰三
居酒屋や ラーメン屋
スナックなどが
十軒ほど入っている
三階建てのビルの
階段を昇っていると
ふいに
頭上を 何かがかすめた
思わず 首をすくめて
三階まで昇ると
踊り場の 天井近くに
燕の巣があった
燕は
扉のないビルの
出入り口から 入って来て
毎年 巣をかけるのだという
わたしのツバメじゃないのよ
スナックのママが笑った
子育ての邪魔にならないように
客たちは
階段の端の方を
そっと 昇り降りしている
ホッと心あたたまるものを感じますね。場所が「スナック」というのもいい。「客たち」の、大人の呑み方まで伝わってくるようです。「ママ」の対応も分るようで、行ってみたくなります。大人の作品というのでしょうか、死や老いを見つめる作品も大事ですが、こういう作品も大切にしたいと思います。「春」というタイトルも冷えた心をあたためてくれる作品だと思いました。
| |
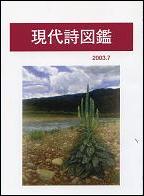 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.7.1 |
| 東京都大田区 |
| ダニエル社 発行 |
| 300円 |
| |
決められない男 嵯峨恵子
電話していいか
夕飯 付き合ってくれないか
以前から
こっちに尋ねてからでないと
行動しない男である
カバンを新調するにも
見る映画を選ぶにも
サケの切り身を一切買うにしても
迷うようなところがある
ドライブしていいか
家に行ってもいいか
好きになってもいいか
いちいち了解を取りたがる
何事もひとりで責任は取りたくないらしい
ママ おやつ食べていい?
先生 プールに入っていいですか?
長年 自分が決断するという訓練を
してこなかった歴史がある
キスしていいか
触ってもいいか
セックスしていいか
いいか
いいか
返事するのも嫌になる
蹴りでも入れてやろうか
自分で考えなさいよ 自分で
女にそっぽをむかれて
男は明日の出張の用意をする
靴下もシャツもパンツも並べて
出張だってむろん部長の許可を取ったのだろう
パジャマに着替えて
さあ 寝ようかという頃になって
やっぱり男は聞くのだ
アイスクリーム食べていいか
そうはおっしゃいますけど、この「男」の気持、少しは判るような気がしますね。まさに「長年 自分が決断するという訓練を/してこなかった歴史がある」んだと思います。「決断」をするのは先生であったり、会社に入ってからは上司であったりして、いざ自分が上司になってみると、やっぱり「部長の許可を取っ」てしまう。そういうふうに私たち「男」は飼い馴らされて来たんだと思います。昔、ノンポリなんて言葉があって、社会はノンポリを望んでいましたからね、それに身丈を合わさないといけなかったわけです。それを今さら責められても、、、と、ついつい「男」の肩を持ちたくなりました。
もちろんそんな中でも気概を持ってる奴はたくさんいたし、今だに反骨の塊みたいな奴はいます。はて、オレはどっちだろう? と、ついつい我が身を振り返ってみた作品です。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.7.1 |
| 東京都中野区 |
| 新日本文学会 発行 |
| 851円 |
| |
カラクム砂漠の村 白井知子
プハラからオリモザ村まで
遥か ぽつりぽつり 灯が見えていたが
しだいに闇だけ 砂漠の中を走っていく
道の両脇の闇が盛りあがってくる
パンクしたタイヤを外し
ジャスールが溝のない古タイヤに替えた
万事うまく行ったと身振りで告げ
彼は再び車を走らせた
ヘッドライトが人の姿を映しだした
両手を荷物で塞ぎ 大人の間に子どもを挟み
新月の悪路をぞろぞろ歩いていく
乗合バスの停留所まで夜を徹して歩くのだろうか
車の砂煙が列の後尾を消した
ウズベキスタン プハラ市街から七〇キロ離れたオリモザ村
蜜蜂百箱 牛と羊 鶏 犬
ムスリムのアシュロバ一家七人のもとに
今宵は宿を許され 客となった
夕餉にもてなされた羊料理の
きつい香料と 祈りの声の残る部屋で
女たちの寝息を聴きながら眠る
わたしは七歳になる少女シトラの隣り
小さな鼻息に撫でられても寝つかれない
祖母のムニサは白布ですっぽり覆った頭だけ
毛布から覗かせ その向こう側
二歳の末娘を抱きかかえた母親ショーイラン
男たちは隣室で眠っているはずだ
砂嵐に隠されていた村から
ふいにあらわれた葬列のような足どりで
あの人たちは歩いていた 不機嫌で暗い目
この村に来るときライトが捉えた人の列
幾つの家族が移動していたのだろう
カラクム砂漠を南下すれば
地続きのアフガニスタンまでわずかだ
戦場にされた村々から
夜更けの国境をこちら側に逃れてくる人たちがいる
列の先頭は見えない列に繋がれていく
散らばった肉の破片が人の形に集められた影まで
列に寄りそい 黙々と歩いている
いきなりシトラが声をあげたかと
苦しげに寝返りを打ち しゃくりあげた
祖母のムニサが <ラーラ ラーラ>
背中をさするうち寝息も穏やかになっていく
孤りでたちかえる闇に脅えているのだ
納屋や戸外でうずくまる動物の鼓動
母屋の人間の鼓動 そして聴きいるわたし
こんなにも間近にいるのに――
太古の昔よりもあからさまに
ひたすら <供犠の列> を求め
ひたすら <供犠の血>
に渇いた者たちが
レーダーをかい潜り 黒い機体でしのび寄る
地上で細胞を破滅させるには
これ以上の毒性はのぞめない金属
劣化ウランを芯にした砲弾が地表をえぐる
寝静まった砂漠の村から
体温ある人型のいのちを奪いとるのだ
作者が中央アジア「ウズベキスタン」に旅行したときのことをモチーフにした作品です。見ず知らずの家で「宿を許され 客とな」るのも驚きですが、戦争の影が「シトラ」の「しゃくりあげ」になっているのだろうかと思うと胸を突かれるものがあります。
実際に現地を訪れた者のみが描ける作品だと思います。それも単なる旅行者ではなく、現地と同化しようとまで考えている作者の姿勢が伝わってきます。その姿勢があるからこそ「夜更けの国境をこちら側に逃れてくる人たち」まで見ているのではないでしょうか。冷静に、しかもあたたかく見つめる詩人の眼に敬服しています。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.8.1 |
| 東京都豊島区 |
| 詩人会議 発行 |
| 840円 |
| |
ヤスクニ・ノート 葵生川
玲
沈黙
ガラスの陳列ケースに
びっしりと並んでいるのは、
白無垢の
花嫁人形だ。
沈黙の、
何も語ることなく
こちらをじっと見つめ続ける者は、
軍服姿の 男だ。
視線のこちら側で、
死が隔てた
断ち難い連綿とした肉親の想いに飾られ、
その想いに寄り添う夥しい人の形。
若くして亡くなった者には、親族の手によって死後
の結婚が執り行われる。
あの世にて、夫婦となっての幸せを願うのである。
花嫁が身にまとう
白無垢は、
もともとは喪服として使われた正装でもあった と。
境内の森を抜けて
そびえ立つ遊就館の、
ガラスケースの中に
静かに 寄り添って並んでいる。
死は、生に連続して
人々の日常の時間を造っているのだ。
「ヤスクニ・ノート」という総題のもとに「ラジオ実況放送」「夏」「腐食」「白鳩課」「場所」「公式参拝」「沈黙」「復活―新遊就館再開」という詩が載せられています。全部で14頁にも及ぶ大作です。靖国神社だけをテーマにしたこれほどの力作を私は他に知りません。まさに満身の思いで描いた詩群と言えましょう。
紹介した作品はその中の「沈黙」です。「白無垢の/花嫁人形」の異常さに詩人の感覚が研ぎ澄まされていくのが判ります。「親族の手によ」る「あの世にて、夫婦となっての幸せを願う」気持は、実は「死は、生に連続して/人々の日常の時間を造っているのだ」と読み取る詩人・葵生川玲の心境はどんなものだったのでしょうか。「沈黙」というタイトルにそれが表出しているように思います。ぜひ全行を読んでほしい作品です。
| |
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.6.22 |
| 千葉県東金市 |
| 玄の会・高安義郎氏
発行 |
| 1000円 |
| |
九十九里浜 高安ミツ子
塩の香をのせて荒波の音が聞こえます
海が見たいと言っていた義母を
私達は九十九里浜につれてきました
病んだ義母の
残された意識のなつかしさをもとめて
孤を描いて連なっていく浜辺の風景
寄せくる波に描かれた砂模様
義母の幼い記憶はみえるだろうか
夢の世界と現実の境が見えないまま 小さくなった体に
九十九里の浜辺の風は吹きつけています
激しく打ち寄せる波音に壊れていく義母の意識を
更に奪って行くような淋しい怖さを感じたまま
私達はそれぞれの思いを言葉に出せず
光太郎の悲しさを海の向こうから聞いていました
白髪が目立つようになった夫の背中で
今は時間を忘れた蝉のように義母は背負われています
子供達のために力強く生きた義母の心と
ちいさくなった義母の体を
必死に背負う夫の姿に
泣いて散る心の花びらが見えました
かつて地引網で大漁だった九十九里の浜辺は
サーフィンをする若者達でにぎわっています
背負ったまま波打ち際まで歩いても
義母はどんな記憶も拾えないまま
夫の背中ごしに海を見て「広いね」といいました
かつて話してくれた義母の海岸は
天の川のように連なった白砂青松の
絵画の世界でありました
壊れてしまった義母の心と失われた海岸を
春の海風は冷たく色を消していきました
サーフィンの若者が急に遠くかすみ
波打ち際に打ち寄せられた流木のように
互いに分かる切ない感情を折りたたんだまま
夫と私は無言で海を見ていました
「光太郎」の「九十九里浜」、「夫と私」と「義母」の「九十九里浜」、「九十九里浜」という言葉にはどこか寂しい匂いを感じます。たとえ「サーフィンをする若者達でにぎわってい」たとしても、「かつて地引網で大漁だった九十九里の浜辺」を比較するからでしょうか。数えるほどしか行ったことのない私にとっても、「かつて」「天の川のように連なった白砂青松の/絵画の世界であ」ったとしても、それも寂しい匂いのひとつのように感じられます。それは太平洋から「激しく打ち寄せる波音」のせいなのかもしれません。
繰返し作品を読んで、私のその思いは作品から印象付けられたものではないかとも思い直しています。「波打ち際に打ち寄せられた流木のように」「夫と私は無言で海を見てい」たことを見ている、読者としての私。「夫と私」の寂しさを私もまた見たのかもしれません。作品の持つ力に圧倒されたと言ってもいいでしょう。「白髪が目立つようになった夫の背中」は私の背中でもあるのです。
 (7月の部屋へ戻る)
(7月の部屋へ戻る)



![]() (7月の部屋へ戻る)
(7月の部屋へ戻る)![]()