きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.10.22(水)
職場の歓迎会があって、小田原の「金時」という店に行きました。今風の居酒屋ですね。最近できたようで初めての店ですが、なかなかいい処でした。日本酒もそこそこ置いてあって私はもっぱらそれにしましけど、何を呑んだっけかなぁ。この日記は11月23日に書いていますので、かれこれ1ヵ月前のこと。すっかり忘れてしまいました(^^;
4合ぐらい呑んで、そこでバテましたが、八海山・浦霞あたりだったと記憶しています。気持よく呑んだことだけは覚えています。もっとも、お酒を呑むときはいつも気持いいんですけどね。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.10.5 |
| 茨城県龍ヶ崎市 |
| ワニ・プロダクション刊 |
| 2000円+税 |
| |
弟子
しずかな 眩しい光りのなかを
ひとりで立ちつづけなければならなかった。
見えない 荒れた 細いいっぽんの道を
ひとりで 向き合わなければならなかった。
隠されているものは 糸のように
いっぽんに あらわれなければならなかった。
年老いた男は かなしみの筋肉を
樹皮を剥がされた 瘤のある木のように
苦しくくるしく生きなければならなかった。
あの十二人の弟子たちとは そうして
<罪> のなかに 深くふかく
ひとりを 育てられたもののことだから。
キリストと「十二人の弟子たち」をテーマにした作品ですが、キリスト教徒ではない私には深いところは判りません。文意からすると3回出てくる「ひとり」とは著者そのものと受止めることができると思います。最終連はあるいは違うのかもしれませんけど、広義の「十二人の弟子たち」のひとりとして捉えても良いのだろう考えています。詩集全体にも〝個の確立〟を求める、または神から求められているという意識が見えて、襟を正して読みたくなる、そんな思いをしました。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 新・日本現代詩文庫21 |
| 2003.10.26 |
| 東京都新宿区 |
| 土曜美術社出版販売刊 |
| 1400円+税 |
| |
男について
男は知っている
しゃっきりのびた女の
二本の脚の間で
一つの花が
はる
なつ
あき
ふゆ
それぞれの咲きようをするのを
男は透視者のように
それをズバリと云う
女の脳天まで赤らむような
つよい声で
男はねがっている
好きな女が早く死んでくれろ と
女が自分のものだと
なっとくしたいために
空の美しい冬の日に
うしろからやってきて
こう云う
早く死ねよ
棺をかついでやるからな
男は急いでいる
、、、
青いあんずはあかくしよう
バラの蕾はおしひらこう
自分の掌がふれると
女が熟しておちてくる と
神エホバのように信じて
男の掌は
あぶら
いつも脂でしめっている
昨年11月に84歳で亡くなった滝口雅子氏の全詩集です。1984年に土曜美術社より出版された全詩集の再販という位置付けのようです。紹介した作品は1960年書肆ユリイカ刊の第2詩集『鋼鉄の足』に収録されています。
どこかで見たなと思っていましたら、ずいぶん有名な詩のようで1963年の角川文庫『現代詩人全集』から1999年の同じく角川書店『現代詩歌集』まで11回もさまざまな本に収録されているんですね。さらにフランス語、ポーランド語にも訳されているようです。
40年以上前の作品ですが今読んでもまったく遜色がありません。男と女という本質が変らないのだから当然かもしれませんけど、40年前のまだ女性の力がそれほど強くない時期にこのような作品を書いた滝口雅子という詩人に敬服します。女性性からも自由になって発言力の強くなった現代の女性でもここまでの透徹力はないのではないかと思います。男の私の眼から見ても書き得ない作品です。
| |
|
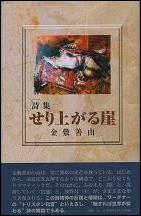 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.8.20 |
| 栃木県宇都宮市 |
| 雁塔舎刊 |
| 2100円+税 |
| |
せり上がる崖J
03―4/25
その頃、水脈のないぼくの街は鳥も棲まないミニザイク
となり、鬱蒼と繁る森も筅(ささら)の径もなくなっていた。気が
ついてみればこの世とやらは、黒と白の繊維に包まれた
事件が余りに多いのだ。魂の原風景はなく、振り切ろう
としても用意に振り切れない野獣の牙を、僕はいつも後
ろから感じていた。運命の日だった。ぼくと連れ添った
女がぼくからの人工呼吸を受けながら、その甲斐なく死
んじまった。
彼女の生き方は譬えば何にもまして容赦なく崖にむかっ
て歩き始まることだ。ぼくはそれを深く識る由もなく女
を愛してしまった。その頃ぼくの庭には女のたましいの
ようにするどいカラタチの花が真っ盛りだった。枸橘の
刺にさされたぼくは血を流して空霧のなかを一晩中ある
いていた。あるき疲労れてぼくは戦意喪失して道ばたの
くさむらのなかへ仰向けに眠ってしまった。ぼくが寝て
いる間も身もしらぬきつねや企み深い世の狸たちは、抜
け抜けと高級車を走らせていた。それから野犬が吠える
夜、悲しいほど女は身を反らして走って行った。
ぼくはそれまでの定職を売り払って下水のなかに躍る
ぼうふらとなりすましやがては蚊になって血の匂いに襲
いかかる。ところがぼくはそれどころか女が幸い身につ
けた英語の塾でたつきを凌ぐ事が出来たので、ぼくは極
楽トンボになり、六畳の部屋いっぱい買ってきた油絵の
具をぶちまけてエーゼルにモデル無しの裸婦を描くのが
日課となった。腰から下を喘息の発作のようにふるわせ
ぼくは空想で描いた女とからみ合っていた。こうして一
枚の絵が描きおわると、また二枚目の絵にぼくは夢中に
なり、二枚目の絵が終わるとまたさらに三枚目の絵を追っ
掛けながら一日がなくなる。しかし金もないのにそんな
楽園が何日も続く筈もなかった。ぼくの心がエーゼルの
中の女と熱く抱き合った時間も飛び散って女に愛想つか
され日常が突然帰ってきた。ぼくはそれから尻尾を垂れ
た犬のように女の言う通りになった。女の強烈な射手座
の根とぼくの魚座の根とが猛暑のようにからみあって辺
りには汗の匂いを隙間なく発散させていた。
陽が沈み夏が去り気がついてみれば激しく雪の降る日
であった。烏賊墨を流したような空の色がぼくと女の訣
別をちょうど告げる前兆のようだった。それでも女は何
喰わぬ顔で洗濯物を乳房のうえまでたくし上げてアパー
トの階段を上がってゆく。もう一方でぼくの人生が安物
の下着のように風に舞うのだ。空から降ってきた犬の糞
も一緒に踏みながら狂おしくカラオケの舞い。その僕は
舞いながら半ば錯乱しながら死んだ女を強く抱きしめて
いた。女から掠めた金を悪魔祓いのように清めるために、
足下には女が好きだった枸橘の白い花を絨毯代わりに敷
きつめる。人はみな死なば野原を駆け抜ける情念の歌と
なれ、ぼくは海岸線に一列に男と女を並ばせて、僕の演
奏したカラオケを歌うように命じたのだ。そのとき女の
呪いの鬼火かはたまたイカサマか、ぼくの透明な海では
大量の鱶がせり上がる崖となっておどっていたのだ。
タイトルポエムの「せり上がる崖」という作品はAからJまで10編あります。紹介した詩はその最後の作品です。ここでは「大量の鱶がせり上がる崖となって」いますが、他の作品では鯨であったり「女たちの絶え絶えの嗚咽」であったりします。
前詩集『包帯男』もそうでしたが全編散文詩。しかも次々と提示される喩に圧倒されます。個々のフレーズも喩なら一編の作品全体も喩。その集成としての一冊の詩集も喩という、まさに本来の詩がそこには余すところなく表現されていると云えましょう。紹介した作品も「ぼくが寝て/いる間も身もしらぬきつねや企み深い世の狸たちは、抜/け抜けと高級車を走らせていた。」「ぼくはそれまでの定職を売り払って下水のなかに躍る/ぼうふらとなりすまし」「もう一方でぼくの人生が安物/の下着のように風に舞うのだ。」など、どこかで使ってみたい言葉で充満しています。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.10.20 |
| 東京都渋谷区 |
| 宮崎由紀氏 発行 |
| 300円 |
| |
家族の食卓 牧葉りひろ
いつの頃からだろうか
お父さんが食卓から消えたのは
七輪で魚を焼いていた頃
井戸で水を汲んでいた頃は
いたような気がする
家にテレビが入り
新幹線が走るようになった頃かもしれない
お父さんは夕べの食卓からいなくなり
休みの日にもいなくなっていた
いつの頃からだろうか
お母さんも食卓からいなくなっていた
残された子どもたちは
冷えたおかずをチンしたり
「お弁当」を買うようになった
それは又
ハラッパがビルになり
露地から子どもの声が消えたのと
機を一にしている
そして
二四時間営業の店ができ
塾帰りの子どもたちが
するあてもない若者たちが
夜立ち寄るようになった頃である
少年が何か事件を起こすと
家庭はどうした
母親は何をしてきたのだと
責めたてる人々がいる。
早く帰れるものなら
暖かい夕食を
家族一緒に食べられるものならと
大抵の
お父さんお母さんは思っているはずである
いつの頃からだろうか
「働く」という字から
「人」という意味が消えたのは
「七輪」「井戸」というのは私にも経験がありますから、この作品には共感します。毎日の少しずつの変化で気づかないで来ましたが、こうやって改めて示されると「家にテレビが入り/新幹線が走るようになった」り「冷えたおかずをチンしたり/『お弁当』を買うようになった」り「二四時間営業の店ができ」たりして、結局は大きな変化の中にいたのだと思い知らされます。その結果として夜遅くまで働いたり休日出勤したりするのは当り前と慣らされてきましたけど、やはり「家族一緒に食べられるものならと」私も思いますね。
最終連は見事です。「人」のために「働く」という行為があったはず、この言葉を今の仕事の中にも生かしていきたいと思いました。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| 2003.10 |
| 東京都品川区 |
| 原詩人社・井之川
巨氏 発行 |
| 200円 |
| |
いらぬおせわだ 竹内
元
いらぬおせわだ
政治が病気の治療に介入して
なにか良いことあるか
犯罪を犯さぬように治療してから
社会に復帰させるのだと
社会復帰という名のもとで
できもしない犯罪予測で一生出さんということだ
病気は悪か 障害は悪か
政治が障害の改善と言うとき
障害を持っていることが悪いのだと
あるがままに生きてはだめなのだと
俺は20年間病気とつきあい
病気のなかでいかに生きやすくするか
障害とどうつきあうか
おりあいをつけて生きてきた
政治は障害が犯罪につながると言い
障害を改善しようとしない者は
矯正治療するのだと
20年以上続いた病気が
簡単に治るものなら治しているさ
治らないからつきあうのとちがうか
おせっかいな政治が
おせっかいなことを始めた
俺らがやめてくれというのも聞かず
俺らと話し合うのもいやだと
歴史を繰り返すのか
ハンセン病のあやまちを
隔離収容のおろかさを
政治はまだ繰り返すのだと
いらぬおせわだやめてくれ
国の政策というのは誰のためのものかということをこの作品を通じて改めて考えています。作中の「ハンセン病」について国が非を認めたのはつい最近のことです。「隔離収容」する必要のなかった病者を70年も80年も隔離してきた、その非が判ったのちも隔離を続けたという恐ろしい現実を考えたとき、「いらぬおせわだ」と書く作者の怖れをもまた感じ取ります。「政治が病気の治療に介入」することを通して政治の本質を訴えている秀作と思います。
 (10月の部屋へ戻る)
(10月の部屋へ戻る)



![]() (10月の部屋へ戻る)
(10月の部屋へ戻る)![]()