きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.11.16(日)
日曜日ですが出勤しました。営業の担当者が新幹線で小田原駅まで試料を持ってくることになっており、それも取りに行って、全てが終ったのが13時半。昼メシも10分ほどで済まして、14時には帰宅できたから、まあまあだったかな。夜まで掛かると一日が丸ツブレになってしまいますからね。まあ、半日ぐらいの出勤ならそれほどキツクありません。それより、仕事が進むことの方がうれしいです。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.11.10 |
| 大阪市北区 |
| 竹林館刊 |
| 2000円+税 |
| |
定年七景
<退屈>
たんねん
背を丸くして妻が丹念にたたむ
せいふく
明日からは着ることもない制服
どこにしまい込むのか
けはい
その気配を追って耳が動く
ゴン太がうかがいの目で尾を振って
抱いてやったがすぐおろす
ひなが
これからは日永を抱くのだ
けげん
怪訝そうな頗など しないでよ
もっと楽しくなるはずだった
カレンダーがねじれたようで
めざ
目覚まし時計があくびをする
いつにない妻の長電話に ぼんやり惹かれる
新聞もテレビもつまらない
どんどん わがままに転ぶうち
がっき
学生のころの楽器を思い出す
バンド仲間を大事にしとくのだった
胸のネズミがくたびれた手帳を繰る
らくが
ほとんどの電話帳は ただの落書き
どうりょう
同僚なら今ごろ 手が空いている
デスクの電話に あいつが出たらどうなる
「定年七景」という総タイトルのもとに「<ネクタイ>」「<体をちぎって>」「<ネコ>」「<退屈>」「<サーカス>」「<かかし>」「<一生一篇>」という7編の作品が収録されていました。紹介した詩はそのうちの1編です。著者は歯科医を永年勤めた、とありましたから、一般の〝定年〟というのが馴染まないようにも思いますので、創作と受止めてよいのかもしれません。私は定年にはちょっと間がありますから、書かれた内容の全てが理解できるわけではありませんけど、想像はつきます。実際には「退屈」になってしまうものかもしれませんね。そんな雰囲気がよく表現されている作品だと思いました。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.11.20 |
| 神戸市北区 |
| 江口 節氏 発行 |
| 非売品 |
| |
帰郷 松本衆司
今までのことを、ぼくは忘れてはいない。こ
うして、時代の季節を生きて来た。生き延び
て来た。この白線で囲まれた狭い空間で。ぼ
くはぼくばかりを愛し、そして、ぼくを遠ざ
けて。飛び出すこともできず。
トミタ、フジイ、リョウ、サタケ
もう一度、一緒にコーヒーが飲みたい
語りたい、旅をしたい
あの日、あの時を、ぼくのまぶたは色までも
記憶している
そこまで戻ろう
傍線をひいたあの箇所まで戻ろう
あのガリガリとなる鉄筆と謄写版、遠くを見
つめ続けた双眼鏡は、どうしたか。あの手作
りのヒコウキは、傷ついた少年をどこへ連れ
て行った。そして、少年を愛した若い母はど
こへ行ってしまったのだ。
牛窓を訪ねたのは、いつだったのだろう
サタケと一緒だった
海を望む丘の上で、来る年も来る年も、五月
の光を浴びたオリーブの樹を描きつづけてい
る老画家。若い頃、ピサロ、セザンヌに魅せ
られた画家は、七十年、祈りの姿勢で絵を描
きつづけた。十和田奥入瀬で、牛窓で写生し
た絵は、その場所に置き去りにして。痩せた
体に身につけていたものは、古びた長靴と柔
らかなほほ笑みだけだったような気がする。
今、幼い息子を連れ
問いもなく、答えもなく
その老画家の仕種のひとつ一つを思い出して
いる。ぼくも身につけたモノをはずす。そん
なふうに捨てる。そうすれば、きっと、帰る
場所が、見えてくる。そんな気がして。幼い
息子の掌を握る。五月の光を浴びた、小さな
願い事のような手。
人生を「生き延びて来た」と定義する作者の心境が痛いほど伝わってくる作品です。そして「傍線をひいたあの箇所まで戻ろう」と思うのは作者ばかりではないように思います。我々もまた、そこに戻りたがっているのかもしれません。
「幼い息子」の「小さな願い事のような手」という表現もいいですね。「少年を愛した若い母」から「ぼく」、そして「幼い息子」へとつながる生命の連鎖。その中でのフとした人生の回想、そんな思いが伝わってきた作品です。
| |
|
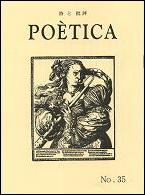 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.10.20 |
| 東京都豊島区 |
| 中島 登氏 発行 |
| 500円 |
| |
詩が歩みはじめるとき 中島
登
1
黄ばみはじめた森のなかを
一頭の駿馬がひた走るひた走る
獅子に追われるでもなく
ただひた走るひた走る
たてがみのない幻の馬
森のおくに泉をさがして
2
険しい山が崩れている
幾層にもわたって
山脈は重なりあっている
どの嶺嶺も兄弟のように
助け合い労りあって立っている
険しい山が崩れている
猪が里へ下りてくる
3
鳥は眼を閉じ
薄明を飛ぶ
狂風に翼をちぎられ
眼を抉られ
鳥は飛ぶ
盲の鳥は飛ぶ
彼方の永遠にむかって
4
タオルを絞ったら貨幣が出てきた
もっと絞ったら紙幣が出てきた
万札だ
もっとタオルを絞ったらドル札が出てきた
ドル札を思いっきり絞ったら
兵士が五人出てきた
みんなイラクで死んだ兵士たちだった
5
ビルばかり蔓草のように高く伸びて
ニコライ堂が見えなくなった
遠景は空しく薄日がもれて
ビルの網入りガラスが
一斉に異様な光を反射する
ビルばかり茨のように天に伸びて
ニコライ堂は海の底に沈む
夕暮れの鐘は深海に響きわたり
かぎりなく低音の祈りの声をのこす
6
若い女はいつしか白髪になった
若い男もいつしか白髪になった
二人は並んで月見草が花開く
瞬間を待っていた
巨きな卵黄色の月が
のぼっていった
女は男を見つめた
男は女を見つめた
7
懐かしい
思いでの壷が帰ってきた
伊万里の染め付けの壷
が車に乗って凱旋してきた
亡き人の鋼鉄の眼の奥に
こんこんと湧き出る泉が隠されていたことを
その時はじめて知った
8
栗の実はぜて
柔らかい幼児の掌に落ちた
栗のいがは痛い
が泣くのは我慢
筑波の嶺から風が吹く
人生にはもっと痛いいがが
沢山あるぞと栗の木が囁いた
幼児の耳のおくのほうに
栗の囁きがとどいた
9
嵐のまっただ中で
ぼくはへどを吐き
へどを吐きながら
海図に線を引き方位を測る
船も唸りへどを吐き
浪を蹴散らしへどを吐く
試験官は赤い顔して
嵐を睨む
が 嵐の顔は見えない
怒り狂っているが姿はない
烈風と荒波が進路をはばみ
後甲板のへどを洗い流す
ぼくはへどまみれのタオルを
床に投げ捨てる
10
なまめかしい
夜明けまえのレインボー・ブリッジ
なまめかしい
中皿のカルパッチョ
なまめかしい
中古パソコン・ショップのデジタルカメラ
なまめかしい
プールサイドのデッキチェア
なまめかしい
日焼けした女の背中の黒子
なまめかしい
払暁に港湾を出てゆく
漁船のエンジンの響き
なまめかしい
真昼のセールのはためき
なまめかしい
投錨しそこなった船の左舷に這い上がろうとする
濡れた髪の処女のにのうで
ちょっと長い作品ですが全行を紹介してみました。「詩が歩みはじめるとき」ですから、ある意味では詩作の秘密を書いたものとも云えましょう。そんな思いもあって全行紹介を試みた次第です。
特に「4」と「10」は興味深いですね。「4」の簡潔な分析と想像・創造、「10」のリフレインに中島登という詩人の本質が見え隠れしているように思います。自分の詩作にも刺激を受けた作品です。
 (11月の部屋へ戻る)
(11月の部屋へ戻る)



![]() (11月の部屋へ戻る)
(11月の部屋へ戻る)![]()