きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
 |
|
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia
godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
2003.12.15(月)
会社の仕事が終えたのが19時過ぎ。仕事というのは切りがなくて、22時でも0時でも、居ようと思えば何時でも居られます。でも、どこかで切り上げないと際限もなく居残ることになりますから、区切りがついたところでやめてしまいました。後ろ髪を引かれるのですけどね。このタイミングが難しいところです。ま、どうでもいいことですけど、毎日そんなことを感じながら仕事をしています。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.5.20 |
| 鹿児島県鹿児島市 |
| 解纜社・杢田瑛二氏
発行 |
| 非売品 |
| |
手紙 西田義篤
久しぶりに実家に立ち寄ると
庭は荒れていた
春の嵐が乱していったせいもあるが
人の住まなくなった家の庭は
すこしずつ形を崩していくものだ
伸びるにまかせた樹々は遥かに屋根を越え
私の手の負えない高さになっている
椎 山紅葉 犬槇 無患子 山椿 つつじ
太い枝には谷渡りや石斛が着生している
藤や郁子に絡みつかれた甘夏や橙の果樹は
観念したのか花をつけていない
魚木の照葉には間もなく端紅蝶が
産卵に訪れるだろう
鳥が種子を運んできた万両や青木は
群落をつくっているし
私が枯えた海老根蘭はいまが盛りだ
もう庭というより
自然林と呼んだ方がふさわしいかもしれない
四方から新緑の繁みが迫り
家はくらく湿っている
何気なく郵便受けを覗いてみると
父宛の手紙がはいっている
父が急逝して一年近くになるのにと
訝りながら差出人をみるとK氏からだ
K氏は父と同郷で古いつきあいになる
父の葬儀の時 K氏の近況を尋ねた私に
「数年前から入退院をくりかえし
いまは人工呼吸器をつかっている」と
奥さんは声を密めて語ってくれたのだが…
K氏の容態を気遣って
父のことはまだ知らせていないのだろう
父宛の手紙を開封するわけにはいかない
だが封を切らなくても手紙の内容は察しがつく
「早く会いに来て欲しい」と
たどたどしい文字で書かれているはずだ
K氏の最後の手紙であり
父宛の最後の手紙かも知れない
私は筆不精の方ではないが
振り返ってみると
父に手紙を書いた記憶がない
父への頼み事や願い事
折りにふれて気くばりを絶やさない父への
感謝の気持ちも
母への手紙にまぎれこませた
正座の姿勢を決して崩さないような
厳格な教育者だった父
そんな父と争い背を向けたこともあったが
父を疎んじていた訳ではない
父はいつも遠くにいた
そう感じていたのは私が距離をおいていたからだといまはわかる
父は私からの手紙を待っていたのだろうか
どんな痛みがあったのか
父は樹を切ろうとしなかった
不恰好に枝をのばした樹の下で
父とK氏が談笑していた姿が眼に浮ぶ
それはずいぶん遠い日のようでもあり昨日のようにも思われる
K氏の手紙をどのようにして父に届けようか
そしてどんな文を添えようか
木洩れ日のなかで私は思案している
「K氏の最後の手紙であり/父宛の最後の手紙かも知れない」手紙を「どのようにして父に届けようか」と困惑している「私」が良く出ている作品だと思います。また「父」という人間が過不足なく描かれていて、作者の視線の深さを感じます。導入部の第1連も具体的にイメージが浮かんできて、2連以降への橋渡しとしては成功していると云えましょう。
肉親との、特に男にとっての父親というのは「距離」がとり難いものですが、その感覚がうまく描かれている秀作だと思いました。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.7.31 |
| 鹿児島県鹿児島市 |
| 解纜社・杢田瑛二氏
発行 |
| 非売品 |
| |
逆転 今辻和典
周代の故事によると
神はふたりに夢を与えた
苛酷な労役で瀕死にある奴隷には
夜ごと王となり快楽を貪る夢を
残忍な権勢を振るう王には
夜ごと奴隷となり鞭打たれる夢を
深夜 ふたりの地位が逆転する
高笑いと悲鳴の輪番制となる
神も洒落れた差配をするものだ
いずれが真の自分なのか
昼と夜の棒の両端を呑みつつ
ふたりは次第に発狂しただろう
逆転 おりおりの幻想であった
果たされることもない革命に似て
希望のようにポケットにあった
神が自分に与える夢の役割は
いつも追われて足すくむ被害者
斬りつける殺陣師に反転したいのに
いま世は酸素が薄れている
不況の錘にじりじりと沈み
どこも生ぬるい風と水温のみ
平和もどこか破傷風気味だ
応急手当のガーゼが貼られる
ひそかな傷の転移は止みそうもない
ひとときの逆転の興奮は
贔屓チームの土壇場の本塁打のみ
映像は再び湿ったニュースに入る
遠く夢見る逆転の逆転そして逆転
でも神がそっと耳打ちするのは
生から死への確かな逆転話だけ
「いま世は酸素が薄れている」「平和もどこか破傷風気味だ」というフレーズが魅力的ですが、やはり「でも神がそっと耳打ちするのは/生から死への確かな逆転話だけ」という最終連のフレーズは圧巻ですね。「逆転 おりおりの幻想」であるのかもしれませんが、最後は本当の「逆転」なのだと納得させられます。人生の何たるかを教えてくれた作品です。
| |
|
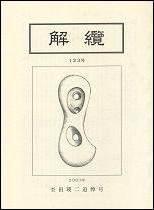 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.11.15 |
| 鹿児島県日置郡伊集院町 |
| 解纜社・西田義篤氏
発行 |
| 非売品 |
| |
冬から春へ 杢田瑛二
いっさんに日は冬に傾く
いっとき黄金色(きんいろ)にきらめいた記憶すら
過ぎてみれば あえなく消える
いま地に丈高く立つ半開きの傘
枝もうすく 風がすうすう通る
しかし無機物ではない
脈打つ鼓動はおくのほうでなお強いのだ
衿持もって公孫樹の精
この際 旅僧となって各地を巡ることを考える
カラン静まる冬のはじめの日
ついに意を決して旅に出る
日々 見知らぬ町や村を通り過ぎていく
いまどのあたりだろう
もはやどれほどの野を過ぎ峠を越えたことか
みぞれ降る町の露地をめぐったりした
記憶たぐれば町の外れにそそり立っていた同輩や
沼のほとりで影写し蕭条と風に吹かれていた
また山の中腹に少しねじれて
あるいは学校の校庭にぽつんと立つ孤影など
冬だから葉一枚無く
光らず豊かに撓うこともなく
みな寒中にあった
その同類の痩せた存在感にほだされ
ときに旅僧の身をひたと寄り添わせようとした
だが一度もそうできなかった
分に応じ生きる気魄をみんな強くうちで燃やしていた
春が近いのか
どうやら発芽したらしい空気にうながされ
ときどき鴬が鳴きだしていた
すると脚は帰路に向っていた
行くたび腰のあたりで鈴がりんりんと鳴る
旅も無駄ではなかったのだ
充実のおもい満ちていまわが身鈴振るごとくあるのだ
まもなく公園の入口――
わが常在の場所に帰り着く
土のにおいを嗅ぐと心地よかった
旅の衣を脱ぎわが家の幹を撫でて中にはいる
すると樹液がゆっくりとわが身をくるむ
快よくなり思わず手をあげて伸びをする
と亭々と立つ梢が一揺れして
青空にむかって
オウーと時ならず声をあげるのを開く
この作品は杢田氏の詩稿ノートの最後に記されていたものを
西田・石峰で判読して起こしたものです。
今号は8月に亡くなった主宰・杢田瑛二氏の追悼号になっていました。紹介した作品は註にもあるように杢田氏の絶筆と思われます。最期まで詩を書き続けた詩人の魂に敬服しています。作品にもお人柄にも接したことのない詩人でしたが、作品から詩にも人生にも真摯な態度が窺えます。ご冥福をお祈りいたします。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2003.12.10 |
| 茨城県龍ヶ崎市 |
| ワニ・プロダクション
発行 |
| 400円 |
| |
秋のはなしぶり 福原恒雄
真っ赤なサルビアを蹴散らしてやって釆たような友なのに
水の所望もない
風のにおいを撫でながら
見てくれのいい
談笑になっていくのを気にしたのか
腋にはさみこんで
思いだしたように
秋だねえ と真顔の呼吸に取り換える
きのうの色つきトンボはいないよ
澄ましこんだお調子者の行方は追わないよ
ミズスマシのほうがもっと逃げ足は速かったぜ
漆かぶれのヤマカガシも風向きを窺っているそうだ
風のせいでも時代のせいでもないわいな
虫食い穴のあいたことばを糊塗する
微笑みは
天下無敵
どこへでも滑る
滑る風が
見渡す限りのぶよぶよの灰燼から
夏から燃え燻って鼻つく髪のにおいが泡立つ日ざしを
きょうから
きょうまで歩いた
句読点で
痞える唾
のみこむ唇を
ざらざらの舌で舐めては
気忙しい時間を突っつき
診断ドックでも影つくらなかった固い胸の殻に
韻を
捨てそうな
たがいの綻びをなすりつけ
失調しそうな行方でも
行方のありそうな窓から見る通りに
展望を塗りたくったポスターで見た展覧会へ向かう
絶えないながれに
うっかり
焦げてもまたそよぐかなと ハモるつもりのない呟き
ススキの言い方にそっくりだ
秋を表現するのに、このような手法があるのかと驚きますね。秋とは異質な言葉がたくさん出てきますが、よく見るとちゃんと秋と繋がっています。人間は出てきません。全部、秋。でも、秋そのものが人間なんです。季節をどう読むかによって即物になったり擬人化されたり、という実例だろうと思います。「秋のはなしぶり」を、耳を澄ませて何度も聴いてみました。
 (12月の部屋へ戻る)
(12月の部屋へ戻る)



![]() (12月の部屋へ戻る)
(12月の部屋へ戻る)![]()