きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
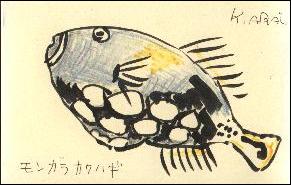 |
|
| |
| |
| モンガラカワハギ |
| 新井克彦画 |
| |
2004.3.27(土)
日本ペンクラブで例会の司会をやっている理事・早乙女貢さんには全13巻の『会津士魂』という名著があります。幕末の戊辰戦争で賊軍となった会津は、実は薩長の理不尽な犠牲であるという筋なのですが、会津藩の支藩・平藩の末裔である私には自分の出自を考えさせられた作品で、少なからぬ影響を受けています。その続編『続
会津士魂』が文庫になっているのを知ったのは最近のことです。全8巻のようですが書店にあったのは7巻まで。8巻目は近く出版されるのかもしれませんね。
終日、それを読んでいて4巻目まで来ました。会津藩が移封になって、下北半島を中心とした斗南藩として再結集したところです。これからどうなっていくのか、歴史の〝正史〟には現れない敗者の視点が新鮮です。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.3.30 |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 |
| ERAの会・北岡淳子氏
発行 |
| 500円 |
| |
風の後に 中村不二夫
深夜 ぼくは一瞬呼吸を止める
かたわらの猫の眠りに
奇妙な安らぎを覚えている
ぼくの肉体は老いたわけではないのに
一昨日からの雨にずっと沈んだきりだ
すべての風景が消されて ぼくがいる
ぼくが住んでいた町 あの人がいて
だれもが笑みを絶やさず 天を仰ぎ
まるでそこは永遠を待つ広場だった
ぼくの生きる場所はどこにあるのか
問いつづけて 再び眠りに入る
今にも消え入りそうな 猫の呼吸
やってくるものに抗うように
無言で旗を降ろしてきた 遥かな日々
だれにも正体を明かさずに
猫は死に場所を定めにいくという
いつしか猫はぼくの体を擦り抜けていた
ぼくは猫を追い 無人の朝の墓地にいた
だれかの声に呼ばれるように
ひたすら坂を昇りつづけている
ぼくの体から しだいに剥がされる物や人
風に倒れる墓標 それを払い除け前に進む
何も残らなかった ぼくを呼ぶ声の他は
いつしかぼくは猫の行方を見失った
それでも ずっと坂は続いている
夜明け前 再びぼくが起つ日まで
「深夜」の「猫」と「ぼく」の不思議な交感。いや、「猫」は何もせず「ぼく」だけが「猫の行方」を追っていたのかもしれません。
「ぼく」には「無言で旗を降ろしてきた 遥かな日々」もあり「だれかの声に呼ばれるように/ひたすら坂を昇りつづけて」日々もあったが、今は「ぼくを呼ぶ声の他は」「何も残らなかった」。同じ時代を生きてきた私にとっても同様な思いがあります。「それでも ずっと坂は続いている」という感覚も理解できるように思います。大事なのは「夜明け前 再びぼくが起つ日」があるのだという認識でしょう。「風の後に」もそれらを引き摺りながら生きていかざるを得ない、そんな新たな決意のようなものを感じた作品です。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 2004.3.15 |
| 神戸市兵庫区 |
| 輪の会・伊勢田史郎氏
発行 |
| 1000円 |
| |
来る日も来る日も 倉田 茂
Y君、きのうきみは死んだ。長いあいだ仕事にも暮ら
しにも愚痴ひとつこぼさず、ちょっとおしゃれで、若い
ときは新劇の俳優志望だったきみ。何て性格のいいやつ。
ぼくは来る日も来る日も昔のことを書いている。ほら、
きみも知っている大して上手くない文章で。Y君、ぼく
はね、近ごろわかったのだよ、ヴァレリーや多くの先達
が言ったこと、眼前を横切る過去だけがぼくらのあかし
ぼくらの現在なのだということが。
Y君、おっつけぼくも行くだろう。そちらのことは知
らない。きみがいる場所は未来なのだから。
「来る日も来る日も」「眼前を横切る過去だけがぼくらのあかし/ぼくらの現在なのだ」というのは、人生の本質を突いているように思います。その果てとして死があるわけですが、それは「未来なのだ」という視点を新鮮に感じました。「未来」に付属するイメージは〝明るさ〟であると私は思っているのですが、死もまた明るいと読み取れて一緒の安堵感を覚えます。「Y君」に向けた言葉はそのまま、現在を生きている私たちへの言葉でしょう。作者の人間を見る眼のあたたかさを感じた作品です。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 2004.4.1 |
| 大阪市北区 |
| 編集工房ノア刊 |
| 2000円+税 |
| |
軒
子供の頃、雨が降ると、私たちはよく軒下で遊んだものだ。農家の軒は、深く広くて、
駆けっこやボール投げのような、行動範囲の広い遊びは勿論できないが、おはじきやお
手玉やままごと遊びのような、座っていてもできる遊びは、殆どできたから、雨が降っ
ても、結構退屈せずに過していたような気がする。
近所のお年寄りたちも寄ってきて、そこで藁仕事などしていたから、私たちは遊びに
飽きると、その傍にべったり座り込んで、藁仕事の様子を見ていて、自然に藁草履の作
り方を覚えたりした。又私たちはお年寄りたちから狐に化された話だの、お化けの話だ
の、土地に伝わる昔噺だのを教えて貰ったりした。
夏になると、大人たちは、そこに縁台を持ち出して将棋をさしたり、夕涼みをしたり
していた。
通りすがりの人が、俄か雨に降られて、駆け込んできたりするのもそこだった。俄か
雨の上りが思ったより遅くなったりすると、その家の人が、駆け込んできた通りすがり
の人に、お茶を振舞ったりした。
私が幼い日を振り返る時、かなりのウェイトをもって、そうした軒下の、人と人との
交歓の様子が、懐かしく思い出されてくる。そこにはいつも、そこはかとない人の温も
りのようなものが漂っていた。
今はもうそのように軒の深い(懐の深い)家は、少なくなっているのではなかろうか。
現に私が住んでいる家も洋風で、軒などと呼ぶには恥しいような突起が、申訳のように
附いているだけである。雨に難渋する人を迎え入れる優しさも、来る人は拒まず、誰と
でも親しく交流する広さも、失われてしまった。日本の家から、軒の深さが消えた時か
ら、日本人の心の深さも消えたのではなかろうか。
詩人でもある著者は、この散文集の特徴を「あとがき」の中で次のように述べています。
この散文集は、文芸同人誌「文学地帯」と、一時期所属しておりました「関西文学」とに、
断続的に発表してきたものを、取り纏めたものです。
元々詩作を主としておりましたため、散文の方は全く自由に、書きたいことを、書きたいス
タイルで、書いて参りました。結果小説的なもの、掌編的なもの、エッセイ的なものと、ジャ
ンルの絞り切れないものが、並ぶことになりました。
「ジャンルの絞り切れないもの」とは著者の衒いでしょうけど、確かに「小説的なもの、掌編的なもの、エッセイ的なもの」が纏められています。紹介した作品はその中でも短いものを選びましたが、日本の原風景と現在とが過不足なく表現されていると思います。特に「軒の深い(懐の深い)家は、少なくなっているのではなかろうか」という指摘は的を射ていると云えましょう。軒の深さは懐の深さ、名言だと思います。肩の凝らない文体の中に人間の歴史を鋭く見ている好著です。
 (3月の部屋へ戻る)
(3月の部屋へ戻る)

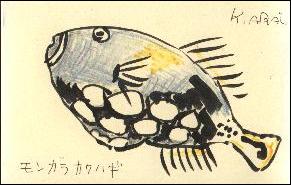
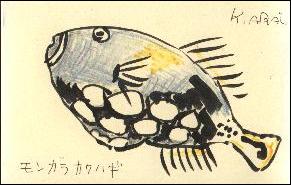
![]() (3月の部屋へ戻る)
(3月の部屋へ戻る)![]()