きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり
】
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 「クモガクレ」 |
| Calumia godeffroyi |
| カワアナゴ科 |
| |
2004.5.19(水)
国語学者の金田一春彦さんが亡くなりました。一度だけお会いしたことがあって、5分ほどお話をさせてもらいました。数年前の日本ペンクラブの例会か日本文藝家協会の集まりだったと思います。会場が開く前にロビーのソファーに座っていたところ、金田一さんが前をお座りになったので、「お元気そうですね」と話しかけたことを覚えています。他愛ない話をしばらく続けましたけど、非常に気さくな方で、初対面とは思えない対応をしていただいて嬉しかったです。91歳で亡くなりましたから、当時は87〜88歳だったろうと思います。ご冥福をお祈りいたします。
| |
|
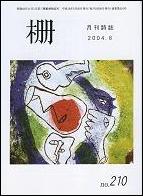 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.5.20 |
| 大阪府豊能郡能勢町 |
| 詩画工房・志賀英夫氏
発行 |
| 600円 |
| |
出発 大貫裕司
日の丸の旗が振られ
軍艦マーチが演奏されて
迷彩服の兵士たちは
静かに出発した
荒れた砂漠の
星空の下に立つことは
ひそかに約束されていたので
長いこと守った不戦の誓いは
脆くも崩れたのだ
崇高な使命の旅立ちへ
隊旗が授けられたが
兵士たちは
遺髪を託したであろうか
聖戦を叫ぶ神の使徒と
聖戦に散った未帰還の兵が
風化した遠景に重なって
悔いはまた繰り返されるのかと いま
無力の空しさにいる
最終連が印象深い作品です。作者は旧軍で兵士となったと記憶していますが、戦争を実際に体験した人には「悔いはまた繰り返される」という思いが、戦争を知らない私たち以上に強いのではないでしょうか。「静かに出発した」「迷彩服の兵士たち」は私よりも若い世代の人たちで、もちろん実戦の経験などあろうはずもありません。「兵士たちは/遺髪を託したであろうか」と問う作者に、彼らはどのように回答するのでしょうか。そんな先人の経験すらも知らずに「崇高な使命の旅立ち」をしたのだろうと思います。
海外派兵が現実となった今、せめて一発の銃弾も発しないように祈るばかりです。日本という国が成り立って以来、一度も銃弾を浴びせたことのない国なのですから。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.5.15 |
| 東京都小平市 |
| 《帆翔の会》岩井昭児氏
発行 |
| 非売品 |
| |
銭湯の匂い 大岳美帆
棺の中に納まったその顔は
妙に艶やかで張りがあり
頬を覆った私の手に伝わった
ぴりりとした冷たさが
でこぼこの現実を突き付けていた
我が子のように
幼い私の面倒をみてくれた
隣のおばちゃん
倒れてから三年間
いろいろなことがあるはずの時間の中で
おばちゃんは一度も家に帰ることなく
白い天井だけ見つめながら
ひっそりと命を繋ぎ止めていた
それでも
彼女の物言えぬ唇が動くとき
私は私の名前を聞いた
おばちゃんが逝ってから数カ月
駅裏をぼんやり歩いていたとき
ふと懐かしい匂いと出会った
おばちゃんと過ごした日々を
鮮明に映し出す匂い
湿り気のある銭湯の匂いだった
おばちゃんの膝の上で
仰向けになった私の首を
片手で支えながら
私の髪を洗うおばちゃんの顔は
思い出せないのだけど
湯浴み客のざわめきと混ざりながら
湯気のこもった高い天井に
反響していた桶の乾いた音が
今聞いたかのように
耳の中に生まれては消える
私は何も
返してあげられなかった
久々に銭湯に浸かり
ざわめきの中で泣いた
第1連の「でこぼこの現実」という詩句に作者の思いが詰まっているように感じます。大好きな「隣のおばちゃん」が亡くなったときの「私」の心理は、まさに「でこぼこ」だったのだろうと想像できます。「彼女の物言えぬ唇が動くとき/私は私の名前を聞いた」ときの、「私」の気持も痛いほど伝わってきました。
「懐かしい匂い」が「湿り気のある銭湯の匂いだった」というのは、作品としても良い設定だと思います。「私」と「隣のおばちゃん」の実在感を感じます。「ざわめきの中で泣いた」「私」の悲しみとともに、人間同士のつき合いとは何かということも考えさせられた作品です。
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 2004.5.20 |
| 神戸市北区 |
| 江口 節氏 発行 |
| 非売品 |
| |
余りのある割り算 彼末れい子
余りのある割り算
それを習った時から だ
わたしの胸は時々不安に波立つ
向こう岸へわたるのに
4人乗りのボートに乗りきれないで
こちら側に取り残された一人
余り1
岸に立ちつくして
(夜の闇が来る)
余りのある割り算
あの時 はじめてわかった
ショートケーキの上に
3個ずつイチゴをのせていくと
最後のケーキには2個しかのらない
余り2は 足りない1
世界は知らないところでねじれてつながり
どちらも同じ
(裏も表もふわふわのカステラの地面)
朝礼台にむかって
39人が4列に並ぶ
余りのある割り算ならば
列の最後尾
一人分のへこみ
わたしは列の中で
そっと後ろをふり向いて見る
誰も余っていない
(そしてそこには誰もやってこない)
「それを習った時から だ/わたしの胸は時々不安に波立つ」という感覚は判りますね。さすがに「ショートケーキの上」までには思いが至りませんでしたが、「世界は知らないところでねじれてつなが」っているというのは判るような気がします。「余り2は 足りない1」という発想はおもしろいと思いました。
最終連はうまくまとめていると思います。「そしてそこには誰もやってこない」というフレーズを括弧で囲っているのも効果的です。おもしろい発想の作品と云えましょう。
 (5月の部屋へ戻る)
(5月の部屋へ戻る)



![]() (5月の部屋へ戻る)
(5月の部屋へ戻る)![]()