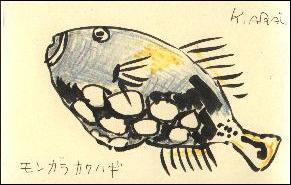 |
||||
| 「モンガラ カワハギ」 | ||||
| 新井克彦画 | ||||
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
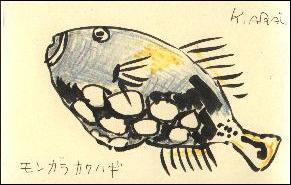 |
||||
| 「モンガラ カワハギ」 | ||||
| 新井克彦画 | ||||
2004.8.26(木)
私だけの強制夏休み6日目。他の皆さんは普通に出勤していて、今日は定時後に定年退職者の祝賀会が予定されています。私も参加申込みをしていましたから、仕事はやらないけどそれだけには参加してきました。盛会でしたね。
一度に全員の写真は撮れなかったのでグループ毎になりました。上の写真が私の所属する部隊です。今回の定年退職者が辞めたあとは、Aさん・Bさん・Cさんと続いて、そのあとが私なんですね。待ち遠しい(^^;
一次会では「浦霞」を呑んで、二次会では焼酎緑茶割り。帰る方向が同じの退職者をタクシーで送って、そのまま帰宅したのが23時過ぎだったでしょうか。明日も休みという安心感があって、ヘロヘロになるまで呑んでしまいました。
| ○中村 純氏詩集『草の家』 | ||||
| 2004.9.1 | ||||
| 東京都新宿区 | ||||
| 土曜美術社出版販売刊 | ||||
| 2000円+税 | ||||
青函連絡船
五戸狐森の雪道を 長いこと歩き疲れ
宿に戻って 布団の中でまどろむ
青森のRAB放送をつけると
青函連絡船のドキュメントが流れた
ひらひらと手を振る人たちを乗せ
函館に向かう船が 遠くなる
過去の時間といとしい人らを
連れ去るように
わたしの旅の道連れは
共に暮らしている人と
青函連絡船での 祖母とわたしの船旅の写真
写真の裏には
「昭和五十年 八・十七 連絡船」と
ボールペンの文字が滲んでいる
過去の空気をふるわせる汽笛の音が
テレビから流れ出す
祖母と五歳のわたしの夏は
上野から寝台車を乗り継いで 青森へ
青森に長期滞在ののち
青函連絡船に乗って 北海道まで
旅は一カ月半にものぼった
祖母はまだ五十代に入ったばかり
わたしは旅の連れに選ばれたことが 誇らしかった
食の細かったわたしに いつも握り飯を持たせた祖母
写真の連絡船のデッキで
わたしは握り飯にくらいついている
うしろで祖母が 海風になびくわたしの髪を撫でている
夜 船の甲板近くの手すりにもたれ
暗い海をじっと眺めていた祖母
闇の海はゴウゴウと音をたて
わたしは祖母の手をぎゅっと握り
初めてだれかを守ろうと思った
テレビは
青函連絡船の終航を 昭和六十四年と伝え
祖母とわたしの旅は終焉だと 理解させようとする
祖母のいのちの旅は 青森で始まり
東京に長く碇泊し
途中 わたしを 旅の同行者として選んだ
わたしは 祖母を青森の地に 連れて帰ってきた
いや 祖母がわたしを この地に連れてきたのかもしれない
祖母の魂は
今 青森の雪原で遊び
役目を終えたわたしに もう帰んな と笑う
生きることは 捨てたもんじゃない
おまえに会えて 楽しかった
そしておまえも 生きていけ
おまえもいとしい人を抱け と
「眠いの?」
穏やかに訊ねる人が
わたしの睫についた涙をのぞきこみ 指先で拭う
わたしは彼の胸に碇泊し
新たないのちの予感に向かって
帆をあげる
著者は30代の若い女性で、第一詩集です。ご出版おめでとうございます。
詩集は3部に分かれていて、祖母の生涯を扱った「浅草・青森 祖母の旅」、祖父の出生地を訪ねる「玄海・釜山 祖父の海」、父母との生活やその他の作品を集めた「草の家」という構成になっていました。紹介した詩は「浅草・青森 祖母の旅」の最後に置かれた作品です。
詩集のタイトルからは「草の家」の章からの作品を紹介しなければならないのでしょうが、著者の性格を形作ったのは祖母にあると読み取れ、その中でも端的に祖母との関係が浮かび上がる「青函連絡船」を紹介する次第です。冒頭の「五戸狐森の雪道を 長いこと歩き疲れ」というフレーズは、祖母の生地・青森県三戸郡五戸町字狐森を訪れたことを言っています。
私の生地は北海道ですので、子供のときから何度も「青函連絡船」を利用していましたから、「闇の海はゴウゴウと音をたて」という表現がよく判ります。それはそれとして、この作品で祖母という人間の描き方はよく出来ていると思います。直接の言葉としては「もう帰んな」「生きることは 捨てたもんじゃない/おまえに会えて 楽しかった/そしておまえも 生きていけ/おまえもいとしい人を抱け」しかありませんが、必要十分に祖母を伝えていると思います。特に「生きることは 捨てたもんじゃない」というフレーズは素晴らしい。将来に残る詩句となるでしょう。
10代の頃から『ラメール』を読んでいたり「詩と思想研究会」にも属しているから当然かもしれませんが、勢いのある詩集に出会えました。新しい詩人の誕生を祝福し、今後のご活躍を祈りたいと思います。
| ○詩・小説・エッセー誌『青い花』48号 | ||||
| 2004.7.20 | ||||
| 東京都東村山市 | ||||
| 青い花社・丸地 守氏 発行 | ||||
| 500円 | ||||
湖畔 神山暁美
ことしの椿は
ひだり眼だけに咲いた
もう右の視力は
花の紅をとらえられない
「潤んだ瞳がきれいだよ」
痛いほどに凝視めるしぐさが
いたずらにキザなことばを誘う
寺の名をもつ湖のほとり
夢の重みでとばなかった
しゃぼん玉の話をしながら
あなたとの時間をほどいていく
若さから解き放たれた季節
みぎの視野を占める
湖水をまとった山の姿
見馴れた稜線の
輪郭がうまくなぞれない
けれど
左側にひろがる青空のなか
色あせた病葉ふたつ
浮かんでいるのがはっきり見える
その身を波にゆだねて
つかず 離れず
決してかさなることなく
「もう右の視力は/花の紅をとらえられない」のは事実かどうか判りませんが、作品上のことと考えましょう。その反対の「左側にひろがる青空のなか/色あせた病葉ふたつ/浮かんでいるのがはっきり見える」ほうが重要だと思います。なぜなら「色あせた」「ふたつ」の「病葉」は「つかず 離れず/決してかさなることなく」「その身を波にゆだねて」いるのですから…。この表現は巧いと思います。「若さから解き放たれた季節」を迎えないと書けないフレーズと云えましょう。
「夢の重み」という詩句もいいですね。結局、人間なんて「あなたとの時間をほどいていく」しかないのだなと妙に納得させられます。しかし「寺の名をもつ湖のほとり」で、そうやって「色あせた病葉ふたつ」は新しい時間を持つのだ、とも考えたいものです。「みぎ」と「左」は別々の道を歩くことになったとしても、「その身」から離れることはできないのですから。
| ○詩誌『火皿』105号 | ||||
| 2004.8.1 | ||||
| 広島市安佐南区 | ||||
| 福谷昭二氏方・火皿詩話会 発行 | ||||
| 500円 | ||||
裂けた空の向こう側 長津功三良
若緑の密集した木立の上から
補修し少し色の変わった鉄骨が見える
明るい初夏の日差しの下の 碑の前で
肩を並べて 写真を撮ったりしている学生たち
アベックもいる
蒼く深い空
潮の満ち始めた川の流れが 止まっている
背後から 市電の通る音がする
あの深い蒼さの向こう側に なにがあるのか
なにもない なにもない
真空 すっからかんの がらんどう
六十年ほど前
あの空が 裂けて
暗黒虚無の向こう側へ 飛んだのだ
みどりと かすか 潮の匂いがしてくる
修学旅行の女学生たちの 高い無邪気な話し声
いま 世の中 なにごともなし
いや この地球の裏側では
また ひとらが 争いごとを している
いつ ここへ くるかもしれない
ふっ飛んだ あの深い空の向こう側
魂たちの 墓場が あるのだろうか
暗黒に引き裂けた あの日の空は
そのまんま
こどもは こどものまんま
少女は 少女の まんまで いるのだろうか
すこし 風が出て 木立の影が
揺れている
日差しは 暑くなりはじめる
深い蒼い空の向こう側
かすか うすれた 影たちの
ゆらめきが
見える
広島の原爆を告発し続ける作者の、抑えた怒りが滲み出ている作品だと思います。「六十年ほど前/あの空が 裂けて/暗黒虚無の向こう側へ 飛ん」で、「真空 すっからかんの がらんどう」になってしまったけど、実は「魂たちの 墓場が ある」。そこでは「こどもは こどものまんま/少女は 少女の まんまで いる」。人生の始まりで命を奪われた「魂たち」へ共感する作者の姿を見ることができます。さらに作者には「かすか うすれた 影たちの/ゆらめき」さえも「見える」のです。そして「この地球の裏側では/また ひとらが 争いごとを している」のも見え、それが「いつ ここへ くるかもしれない」と憂います。抑えたからこそ効果の高い作品になったと思いました。
| ○隔月刊詩誌『石の森』123号 | ||||
| 2004.9.1 | ||||
| 大阪府交野市 | ||||
| 金堀則夫氏 発行 | ||||
| 非売品 | ||||
水のひとみ 奥野祐子
屋根の上から
水滴がすべり落ちる
ためらいもなく まよいもなく
水は
おちるところへ おちるままに
空中に身を躍らせて
静かに地面にたどりつく
水にもし コトバがあるなら
屋根の上ですくみ上がるだろう
その高さに
自分におかれた
ただ おちるしかないという運命を
力の限り呪うだろう
恐怖の叫びをこらえながら
全身を硬直させて
おちるだろう
水にもし コトバがあるなら
でも
水にはそんなもの ありはしない
水をかたちづくる
細い銀の腕を持つ原子たちが
からまり もつれあい
なめらかに抱き合いながら
ほら また
屋根の上をころげおちてゆく
コトバもないのに
原子は互いを求め合い
引き合い
偶然がまるで必然のように
ためらいも まよいもない
一瞬のつながりは
絆のようで
愛のようで
ニンゲンたちよりも はるかに強く
原子たちは愛し合っているようで
雨に打たれ
雨に濡れそぼち
雨のにおいに全身を満たされて
ずっと このまま 少しだけ
やさしいきもちで 立ちつくしていたい
ひとり
私の中の水の原子が
雨を慕い 恋いこがれ
空を見つめる
激しいまなざし
水のひとみ そのものになって
「水をかたちづくる」のは水素結合ですが、それを「細い銀の腕を持つ原子たちが/からまり もつれあい/なめらかに抱き合いながら」と表現しているのは見事だと思います。水は無色無味無臭の液体と教わって、水素結合は単なる線としか考えてきませんでしたけど、「細い銀の腕」と云うのには驚かされます。詩人の言葉だなぁ。物理の分野では『水とはなにか』という有名な本がありますけど、そんなこと書いてなかった(^^;
「原子たちは愛し合っているよう」だ、というフレーズもおもしろい。「私の中の水の原子が」「激しいまなざし」になって「水のひとみ そのものになって」いるというのもいいですね。大人では体重の60%、新生児は80%が水と言われていますから、若い人ほど水の割合が多いのではないかと思います(年寄りが〝枯れる〟と言われるのはこの延長線上の話?)。「水のひとみ」を感じるのは、肉体的にも精神的にも若いからではないかと思った作品です。
![]() (8月の部屋へ戻る)
(8月の部屋へ戻る)
![]()