| |
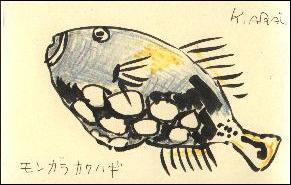 |
|
|
| |
| |
| |
| 「モンガラ カワハギ」 |
| 新井克彦画 |
| |
| |
2004.8.30(月)
9日間に渡った私の2回目の夏休みも昨日で終りました。本当に終ってみればアッという間ですね。
会社に行ってみたら案の定、Eメールも社内メールもどっさり。20時過ぎまで対応しましたけど、結局終らず、あきらめて帰宅しました。まあ、ぼちぼちと片付けていきます。
| |
○植木信子氏詩集『迷宮の祈り』 |
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| 岩礁詩人シリーズ
No.10 |
| 2004.8.18 |
| 静岡県三島市 |
| 岩礁の会 発行 |
| 800円 |
| |
異質そして優しいものに
2 異文化についての
コンヤのまちに
ばらの花が風に舞う
愁いを込めて踊る人よ
その眼差しは天に地に
かなしいほどの愛おしさにみちて
わたしは心の奥底をつかれる
求める愛に近づく想いの深さに
風に舞うばらの花を集め
白いレースに飾る
永遠の花嫁に嫁す女のように
クムラン派の人々が希求したもの
カッパドキアの岩山に隠れ住んだ人々のこと
あの方がガリラヤ湖を渡って来られ
光の中を風がさざ波を寄せるように
そして求めても去って行かれた朝が
風のなかに
ばらの花がふるように
愛の香を残して
この国にしみ込んで地下水のように流れている
はじめての夜明け前に聞いたコーランの響き
異質 それだけで昼には疲れていた精神がほどけてくる
家族を愛し 恋人を求め
それは生き々とした神が介在していた
カッパドキアに隠れ住んだ人たちは
岩山に響くコーランの音の中でも
あの方の愛を語り賛歌を小さく呟いていた
それはどんな祈りだったのだろう
異質がはっきり分かれていなかったころ
その危ない共存の平和を想う
コンヤのまちに
ばらの花が風に舞う
すべてを捨てて従いたくなるのは
わたしは仏教徒で少しのキリスト教徒ではなかったか
この国では
人々は神とともに暮らしていた
神とともに愛を語り家族やまちが民族が在った
わたしを引き戻すものがわたしの民族の同胞であっても
神の響きは
草に緑の葉に土にしみていた
風にばらの花が流れ
そのことが最大の幸福の条件であるかのように
ばらの花がふる
親しげに話しかけてくれた人々
心から笑いかける
わたしの不信が払われ傷がふさがれていく
人は信じるに足りるのだった
どんな境遇 どんな事態にも信じることができるのだった
帰りの空のシルクロード
天山山脈が少し見える席で
遠い昔の人の満ち足りた会話のように
傍らの人と話した
「異質そして優しいものに」という総タイトルのもとに「1 タシケントで」、「2 異文化についての」の作品が収められています。いずれも中近東を旅行したときの作品ですが、ここでは後者を紹介してみました。
「この国では/人々は神とともに暮らしていた」、そんな国の様子と旅人の心境が巧みに描かれていると思います。「神の響き」が「最大の幸福の条件である」という視点はおもしろいと思いますし、「永遠の花嫁に嫁す女のように」というフレーズもいいですね。何ものにも囚われない作者の資質を感じます。体裁の上では薄い詩集ですが内容は濃いと云えましょう。
| |
○隔月刊詩誌『サロン・デ・ポエート』251号 |
| |
|
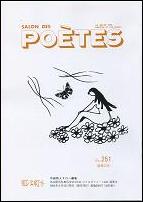 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8.25 |
| 名古屋市名東区 |
| 中部詩人サロン・滝澤和枝氏
発行 |
| 300円 |
| |
森の中 滝澤和枝
どうしてあんなところへ行ったのか それはきっと盲目ってやつの仕業だろう
それとも魔がさしたと 魔物のせいにするのもいいかもしれぬ 十八歳と三ケ月
なんという若さだ ほっペたには春風のような産毛がしっとりと くちびるは赤
い鉱石のようにくっきりと 黒い瞳はどんなものでも砕いてしまう その目が
どうしたというのだ 四十九歳の男の正体を見ないで 一体なにを見たのだ
父親の俺とたった一つしか違わない父親のような男 被っている皮の立派さにだ
まされて 内臓はもう腐りかけているのに 気付かない なんという愚かしさ
誘われるままに よりにもよってあの森へ ともあれ連れ戻さねばなるまい
どこか遠くへ行こうと誘ったのは私 だって父は 四十九歳というだけで反対
母は貧乏だというだけで反対 猛反対 本当は五十二歳で 父よりも一つ上
奥さんも子供もいるって言っちゃえば良かった うそって くせになっちゃう
うそとほんとのスクランブル だからスクランブルエッグはおいしいんだ
世の中なんにもわかっちゃいない と父親は言う でもそれって なに?
わからない わかります わかる時 わかれます ってこと?
知恵と勇気をもった人 頼りがいのあるすばらしい人 森を抜けて行けば
自由な 新しい世界 二人だけの世界がある はずだった
でも森の中で少し ほんの少し休んだだけで あの人は進めなくなった
彼女の若さは弾丸のように襲いかかる 息が切れて立てない 鎧はあっけなく
剥がされて 破れた兵士のように 惨めに倒れてしまった自分の背中を かる
がると飛び越えて まりのように弾んで 披女は行ってしまった
森の中はとても気持ちがよくて 倒れたまま眠ってしまいそうだ この大きな
木と小さな木 じゅうたんのような苔 ずっと昔 家にあった緑のビロード
すり切れたソファー ちょっと湿っぽい 落ち着いた匂いもなつかしい 目の
前に胞子がびっしりと並んで 自分はずいぶんと小さなものになってしまった
森に吸い取られていく 俺の本意かと聞かれれば もちろんそうではないが
森がそうさせる とでもいおうか 俺の死で 娘はより哀しくより深く生きて
いけるようになるだろう あの男 本当は俺よりも一つ年老いているという男
俺の食べ物と水を与えた男 すっかり分別を取り戻し 家族と共により敬虔に
生きていくだろう
森は静かだ 鳥の囀りや虫の羽音 風が渡り 木の葉が落ちる
森はいつだってそのようだ
第1連で父親、第2連では「十八歳と三ケ月」の娘、第3連で「本当は五十二歳」の「四十九歳の男」がそれぞれ出てきて、最終連で再び父親が登場しますが「俺の食べ物と水を与えた」んですね。その結果、父親は死に、「娘はより哀しくより深く生きて/いけるようになるだろう」し、男は「すっかり分別を取り戻し 家族と共により敬虔に/生きていくだろう」という結末になっています。
この解釈はかなり難しいと思います。もちろん〝解釈〟する必要はなく、読者が好きなように鑑賞すれば良いのですが、私には人生そのものの喩に思えてなりません。若い時代に必ず出会う「知恵と勇気をもった人 頼りがいのあるすばらしい人」。そして訪れる「惨めに倒れてしまった自分」。最後には「俺の死」。その背後では常に「森は静か」で、「森はいつだってそのようだ」と云えるでしょう。 しかし「よりにもよってあの森へ」とありますから、「森は静か」なばかりではなく「魔物」のいる場所でもあります。それこそまさに〝世の中〟であると思います。ちょっと強引かもしれませんが、そんな思いで鑑賞した作品です。
| |
○詩誌『EOS』4号 |
| |
|
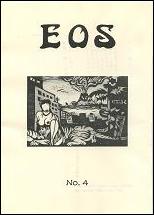 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8.31 |
| 札幌市東区 |
| EOS編集室・安英 晶氏 発行 |
| 500円 |
| |
九月の眼球 小杉元一
世界だなんて口に出すときにはいつもうわずったものさ
おおきな眼球の水死人はそう言う
うわずると
はげしくふりしきる花粉に咳き込みながらいつも海を見失ったと
おおきな眼球の水死人は眼を細め
仰向けのままに脚を広げて右に左に流されながら
動いているのはいつも陸のほうだと思っていた
波は顔を洗い
割れたくちびるをあけたままおおきな眼球の水死人のお喋りは続いていく
たぷたぷと陸は揺れ
陸のひまわりは揺れ
(首のないひまわりは揺れ)
いかにもかるがるとことばは絵文字となって携帯から携帯へ飛びかい
(燃えていく てふてふ)
それにしてもそれにしても
世界を測る巻尺を見失ってからずいぶんと日がたった赤錆びて
まだ校庭の草わらにころがっていた打ち上げられ
海鼠のように干からびていた新しい雨を待ちながら
鳥に銜えられて運ばれていったひとの手の届かない神話の向こう
巻尺の回る音は橋を渡り川面の水は沖に流れ
陸の死者たちは揺れ
(死者たちは揺れながら合唱し)
いかにもかるがるとうたはデジタルに圧縮され解凍され青の薔薇となり
(空から落ちてくる てふてふ)
それにしてもそれにしても
「ビルの窓に玩具のようにひっかかっていたあのセスナ機」の
帆柱の残骸の夢ばかりみていた
おおきな眼球の水死人はそう言う
積乱雲の下にはイカロスのむしられた羽は見えないのに
少年の眼球には砂漠が傷口のように焼きついていて
陸の砂漠は揺れ
(死者たちは水の幻とともに揺れ)
永劫の風景のなかでいくどもアレキサンドルは兜の水を捨てる
(いくども甦り燃えていく てふてふ)
それにしてもそれにしても
羽を広げたまま波間から波間に運ばれながら
おおきな眼球の水死人はずいぶんと陸から遠ざかったと思っていたが
あるとき眼をさますと砂浜に打ち上げられていた
無数のかもめが肉をついばんでいたと言う
白い雨が眼球にふりしきり
陸の雲は揺れ
(樹海は死者たちとともに揺れ)
いかにもかるがると世界は全体になり破片になり液晶になり
(原色の花のあいだを舞う てふてふ)
それにしてもそれにしても
おおきな眼球の水死人は眼球だけとなり
ふたたび波に流され浮上し流れて
九月の眼球 ひとつはゆっくりと沈んでゆき
九月の眼球 ひとつは気ままに波間から波間に揺れ
水はたぷたぷと
「おおきな眼球の水死人」がまるで生きているようで、おもしろい作品だと思いました。それも「世界だなんて口に出すときにはいつもうわずったものさ」、「動いているのはいつも陸のほうだと思っていた」など「お喋りは続いていく」んですからね。「陸の死者」「陸の砂漠」「陸の雲」という類語の繰り返し、「それにしてもそれにしても」「てふてふ」の繰り返しもおもしろいリズムを与えていると思います。
タイトルと最終連に出てくる「九月」も奏功していると云えるでしょう。「水死人」の出やすい7月・8月が終ったあとの月ですから、違和感はありませんでした。その「眼球」の「ひとつはゆっくりと沈んでゆき」、片側の「ひとつは気ままに波間から波間に揺れ」て分かれて行く。この象徴は「水死人」のみならず、生きている(水死人から見れば死んでいるのかもしれない)私たちそのものではないかとも感じます。現代の寓意とも呼ぶべき作品だと思いました。
 (8月の部屋へ戻る)
(8月の部屋へ戻る)

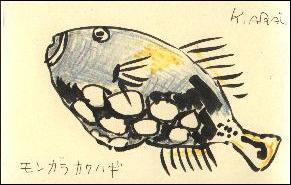
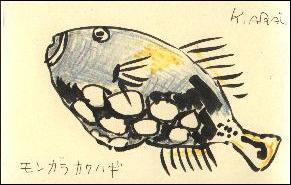
![]() (8月の部屋へ戻る)
(8月の部屋へ戻る)![]()