| |
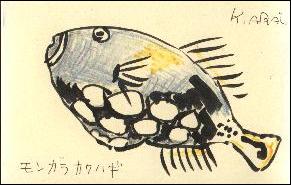 |
|
|
| |
| |
| |
| 「モンガラ カワハギ」 |
| 新井克彦画 |
| |
| |
2004.9.2(木)
9日も休んだあとの週ですから、さすがに今日は疲れました。昨日まではそれほど感じなかったのですが、ようやく出勤4日目で感じられるようになった、ということなんでしょうか。
まあ、そんな程度の一日でした。可もなく不可もなし(^^;
| |
○詩マガジン『PO』114号 |
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8.20 |
| 大阪市北区 |
| 竹林館 発行 |
| 840円 |
| |
木魚 モリグチタカミ
だいじな相談があるというので
運営委員会が開かれた
この小さな会館の五年ごとに掛け替えられる
玄関の絵を選定する会である
新年度から掛けられる絵の候補が二点あって
館長がひとりでは決められないという
Aの絵はいろいろと貢献してくれた人の作品
Bの絵は先代の館長の所有の絵
どちらも水彩画であるが高価なものではないという
二作ともすでに館内に保有されていて
委員は
その両方を見た者 片方だけを見た者 どちらも見ていない者に
わかれる
絵を見ても見なくても
それぞれの委員には義理がからんで
どちらがよいとは言いにくい事情があって
控えめの発言しか出ない会だ
だから討議にはならない
すると早く帰りたがっている一人が立って
わるいけど さきに失礼しますわ
わたしは両方掛けたらいいと思っておりますのでと言う
はあ なるほど そうだ そうだ ということになって
二つの絵は玄関の両側に向かい合わせに掛けられることになった
四月になって会館に立ち寄ると
左に太い樹の幹の浮き出た絵が
右に濃紺の魚が大皿にのった絵が
玄関で向き合って掛けられている
木の絵と魚の絵
絵であるのに「木」と「魚」とから
つい「木魚」が連想されてしまって
これから五年間は入館者を
木魚がお迎えする
いらっしゃいませ
ぽく ぽく
なんともホンノリとさせられる作品で、思わずニンマリしてしまいました。たかが絵1枚を「ひとりでは決められない」「館長」、「絵を見ても見なくても」「控えめの発言しか出ない会」、「はあ なるほど そうだ そうだ」と納得してしまう「委員」たち。まるで童話か御伽噺の世界のようで、いいですね。我を張る人がいない「小さな会館」の「運営委員」の皆さんに思わず拍手。
「いらっしゃいませ/ぽく ぽく」には大笑いしてしまいました。「木の絵と魚の絵」のある「小さな会館」に行ってみたいものだと思ってしまった作品です。
| |
○詩誌『きょうは詩人』11号 |
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8.25 |
| 東京都武蔵野市 |
| 鈴木ユリイカ氏方・きょぅは詩人の会
発行 |
| 500円 |
| |
浴衣 長嶋南子
タンスの底にある
白地に藍色の花もようの浴衣
三十年来いちども手を通したことがない
これを着て
好きな人と連れだって歩くことはなかった
金魚すくいの網は見あたらず
下駄の鼻緒にこすれることもなく
技豆もいっしょに食べなかった
とおに手の届かないむかしになってしまって
浴衣にまつわるものがたりは
ひとつもない
そのあいだにもご飯はしっかり食べて
ときどき茶わんを割ってお皿を割って
そのたびにあたらしいものがたりが生まれ
なにも生み出さなかった浴衣は
寝間着にでもするしかない
前がはだけて
あられもないかっこうになるけどね
「とおに手の届かないむかしになってしまっ」たものの象徴として「三十年来いちども手を通したことがない」「白地に藍色の花もようの浴衣」があるのですね。「ときどき茶わんを割ってお皿を割って/そのたびにあたらしいものがたりが生まれ」たけど、「浴衣にまつわるものがたりは/ひとつもない」。そして「なにも生み出さなかった浴衣は/寝間着にでもするしかない」。でも、気をつけないと「前がはだけて/あられもないかっこうになる」よ。「タンスの底に」仕舞ったままにしておいたものの反逆と読み取れるかもしれません。
そんなふうに私たちの人生は流れていくものなのでしょう。「好きな人と連れだって歩くことはなかった」かもしれないし、別の人とは歩いたかもしれない。それはどちらでも良かったのでしょう、今となってみれば…。そんな怠惰な部分も人生にはあるんだ、そんなことを行間に感じた作品です。
| |
○詩誌『暴徒』52号 |
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8.25 |
| 東京都練馬区 |
| 尾崎幹夫氏方・暴徒社
発行 |
| 400円 |
| |
春へ 尾崎幹夫
雪がふって
ぼくは氷にとざされている
体がうごかない
と おもうとむねにおもりがのしかかり
きょうも外にでられない
ふゆがれのそとを見る
木の枝にこしかけているものがある
脳出血で死んだ父だ
父がいう
外に出てみろ
死ぬまでは生きていられる
その木だけが芽をふいている
体温があがる
ぼくをおおっていた氷が霧になってちる
外に出てみる
青空がある
木の枝に もう父はいない
ぼくはゆっくり歩きはじめる
ちらばっていたこころが
ひとつになる
春を歩こう
光を歩こう
生きていられるうちは生きていよう
「脳出血で死んだ父」に励まされて「外に出てみ」たら、「ちらばっていたこころが/ひとつにな」って「生きていられるうちは生きていよう」と思った、いわば再生の作品ですから「春へ」というタイトルは巧く生きていると思います。「死ぬまでは生きていられる」という当り前のことを詩句として成立させているのも奏功していると云えるでしょう。
「体がうごかない」「ぼくをおおっていた氷が霧になってちる」というのは、おそらく実感なのではないかと思います。詩作品ですから、作者が実際に体調不良なのかどうかは関係ないのですが、そこは不思議に伝わってきますね。いずれにしろ「春を歩」いて「光を歩」いていただきたいものです。
| |
○個人詩誌『点景』29号 |
| |
|
 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| 2004.8 |
| 川崎市川崎区 |
| 卜部昭二氏 発行 |
| 非売品 |
| |
「この肉の歌」より 卜部昭二
この肉は父母からのものと
故郷の茫漠たる大地からのものと
この肉は過去 現在 未来
快の国への欲求を秘め
果てしなく旅する
この肉は眠りの中で夢灯もし
醒めてまた夢見つづける
表紙を飾る巻頭作品です。力強さの中に「果てしなく旅する」「この肉」の本質を見つめているところがさすがだと思いました。最終連もいいですね。結局、「この肉」は「夢」を追い求めているに過ぎないことがよく判るのですが、作者はそれを否定的・諧謔的にはとらえてはいないようです。肯定し、むしろいとおしんでいるように読み取れました。それがこの作品の良さであり、作者の持ち味だと思いました。
 (9月の部屋へ戻る)
(9月の部屋へ戻る)

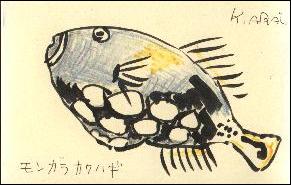
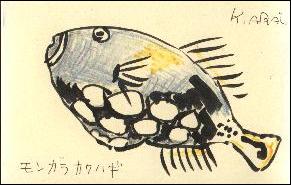
![]() (9月の部屋へ戻る)
(9月の部屋へ戻る)![]()