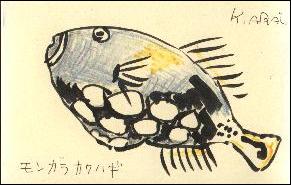 |
||||
| 「モンガラ カワハギ」 | ||||
| 新井克彦画 | ||||
| きょうはこんな日でした 【 ごまめのはぎしり 】 |
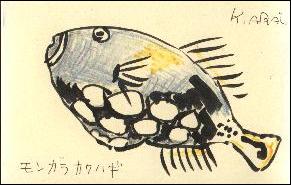 |
||||
| 「モンガラ カワハギ」 | ||||
| 新井克彦画 | ||||
2004.9.10(金)
職場の歓迎会が、私にとっては初めての店でありました。職場から10kmほど離れた料理屋でしたが、送迎にはマイクロバスを出してくれて、幹事としては大助りでしたね。半年に一度、私の自宅に届けてくれる「越乃寒梅」四合瓶3本のうちの1本が残っていたので、持ち込んだのですが、持ち込み料も取られず、その点でも気に入りました。もちろんすぐに呑まれてしまいました。
| 呑み会の一場面です。 女性3人組のバラバラの視線が何とも……。 店のお酒はまあまあ。 日本酒はたいしたものが置いてませんが 焼酎緑茶割りはお薦めかもしれません。 |
| ○詩誌『複眼系』35号 | ||||
| 2004.9.10 | ||||
| 札幌市南区 | ||||
| ねぐんど詩社・佐藤 孝氏 発行 | ||||
| 500円 | ||||
夕食 佐藤 孝
つめ放題百円とかで
ポリ袋に詰めれるだけ詰めて
中国産の推茸を妻がどっさり買ってきた
かさも茎も因果関係を放棄して
詰められるだけ詰められた存在となって テーブルの上に投げ出された
「こんなにあるんだよ どうして食べる? 煮る? バター炒め?」
矢継ぎ早に問い詰められて「うーん」と唸るばかり
<中国とはいえ生産者がこんな無残な売り方を想像もしていないだろう>
妻はもうかることが好きだ
百円でこんなにいっぱい推茸が手に入ったというだけでご機嫌なのである
フライパンにバターを塗ると張り切ってじゃじゃ焼いて
たちまち大皿いっぱいの焼き椎茸が並んだ
中心点に向かって縮んだ跡がリング状の溝をつくり
闇夜を走る特殊部隊の帽子のように整列している
「さぁ どうぞ!」と小皿と箸をそろえられると
平生さが気泡になって抜けていく
昔話に出てくる軒先の干し柿そっくりである
「おじいさんとおばあさんは、毎日、裏山の椎茸を、ご飯にしておったと…」
天井裏からナレーターの声が聞こえそうな静けさ
小皿に移して噛んでみる
ズクッと歯が突き刺さる感触は戦後のしばれ薯を思い出す
バター一色の味である
「バターの味がするね」
「そりやそうよ バター炒めだもの…」
妻も小皿に盛って食べ始める
「中国だかなんだか分からないわね」
「共産主義やめたから…」
「やっぱりバターの味だわ」
「バター焼きだからな」
「そうだね」
「推茸ってこんな味だったかなぁ」
「つめ放題で百円だもの…」
「昔話みたいだね」
「なに?」
「椎茸のことさ」
「……」
四十年一緒でも椎茸の沈黙は伝わらない 夕食である
最終行がいいですね。「昔話」を「妻」には言っていないのですから「伝わらない」のは当り前なんですけど、〝夫〟を永年やっているとこの感覚はよく判ります。それをおそらく「妻」たちは男の身勝手と云うのかもしれません。
「 <中国とはいえ生産者がこんな無残な売り方を想像もしていないだろう>
」というフレーズでは、作者の本質的なやさしさを感じました。「百円でこんなにいっぱい推茸が手に入ったというだけでご機嫌」になる、その向うを見ることが出来る人は意外に少ないように思います。その意味でも勉強させられた作品です。
| ○会報『横浜詩誌交流会会報』51号 | ||||
| 2004.9.1 | ||||
| 横浜市鶴見区 | ||||
| 横浜詩誌交流会事務局・ひらたきよし氏 発行 | ||||
| 非売品 | ||||
親の背中 新井知次(獣の会)
この国の偉い人が
次々とハンカチの中から
白い鳩を空に放った
下手な芝居だったのか
鳩はたちまち黒く変身して
カアカアと鳴きだし
ぼくの頭に
フンを落とした
鉄が湯になって走っている
ぼくの親父は呼吸の熱の現場で
肺を焼いた
百歳まで生きる予定が
ベットに寝たまま
七十二歳で死んだ
焼かれた肺が
下手な手品のカラクリを
ぼくに教えてくれた
アイムソーリ
ソーリが日本語だとすれば
カツラヲカブッタニボシ
スカートヲフマレタオンナ
変わらない斬った張ったのおまつり
変わらない渦巻けるカラスの
降ってくるフンフン
ぼくの髪はすっかり白くなった
親父の肺が教えてくれた
余りにも単純な種明かし
余りにも単純なおまつり
余りにも単純な怖さ
笑えない笑い
「焼かれた肺が/下手な手品のカラクリを/ぼくに教えてくれた」というフレーズは難しいのですが、「鉄が湯になって走っている」とありますから、おそらく製鉄の現場のことを言っているのだと思います。「親父の肺が教えてくれた」ものは「白い鳩を空に放った/下手な芝居」の末の職業病だったと考えています。その犠牲の上に立った高度成長、「変わらない斬った張ったのおまつり」が「親の背中」を通して見えてきたものだと思います。ですから「笑えない笑い」になってしまうのですね。
さて、なかには孫もいる歳になって、私たちはどんな「親の背中」を見せることが出来るのか、それも問われている作品だと思いました。
![]() (9月の部屋へ戻る)
(9月の部屋へ戻る)
![]()