| きょうはこんな日でした【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 新井克彦画:ムラサメ モンガラ |
| きょうはこんな日でした【 ごまめのはぎしり 】 |
 |
| 新井克彦画:ムラサメ モンガラ |
2001.10.24(水)
その2 その1へ
| ○詩と詩論誌『新・現代詩』2号 |
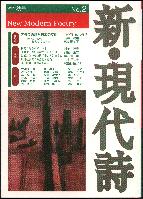 |
| 2001.10.1
横浜市港南区 新・現代詩の会 出海渓也氏発行 850円 |
血の丸/草津信男
ペン先から赤インクがボタ落ちしたのか
畳の上に拡げた白布のうえに
指先ほどのまっ赤な染み一つ。
大事なものが汚れてしまった。
急いで水洗いしたが
とれそうにない。
ブリーチを入れ洗濯機を廻してみると消えるどころか少し大きくなった気配。
夜も更けてくるので
仕方なく庭の物千しにかけて寝た。
翌日は祝祭日。
わたしを叩き起こす早朝の雷鳴。
物干し場に馳けつけると
満月のように大きくなってる赤い円型の染み。
日の丸みたいだ。
お早ようございます。
祝祭日は旗日。
欠かさず日の丸を掲げる口うるさいおばさんが
庭の物干しを見上げ愛想のよい声をかけて通りすぎた。
錯覚かもしれない。
気になるので
布の両端をつまみあげると
風があたるたび
まんなかの大きな赤い染みから
雫のようなものがしだたるではないか。
掌についた血。
ああ、血の丸だった
日の丸。
私事で恐縮ですが、ここしばらく私も「日の丸」について考えていました。先日、私の所属する同人誌の次号にも「日の丸」について書いた詩を送ったばかりです。それは、満州事変の古い映像を見ていたら、白黒フィルム故に白地に黒い丸が進軍していた、というものですが、この作品にも同じような思いがあることを知りました。黒い「日の丸」より「血の丸」の方が強烈な印象を与えますがね。
この作品で私がすごいなと思った点は「欠かさず日の丸を掲げる口うるさいおばさんが」というフレーズです。これがあることによって作品の広がりを感じます。「日の丸」が置かれている位置を、ある程度正確に知ることができ、なにより「わたし」以外の人間がでてきたことによって、その「おばさん」が「愛想のよい声をかけ」ることによって、立体化したと思います。これは私には考え至らなかった点で、勉強させられました。
| ○釉彩詩誌No.2『花の迷路』 |
 |
| 2001.4.23
栃木県茂木町 彩工房・釉彩氏発行 非売品 |
あじさいの花は薄桃色
観音様が好きだ
観音様が好きだ
彫った痛みを忘れたいから
観音様にすがる
雨に
濡れつづけなければ
生きていけない
紫陽花のあでやかさは
女の秘めた
罪
女は花だから
女は罪だから
手折られた罪は
ひとりでは負えない
女は花だ、あるいは(花だからこそ)罪だ、という第3連にまず新しい感覚を覚えます。そして「手折られた罪は/ひとりでは負えない」という最終連に、女性のみならず人類の本質的な弱さを感じてしまいます。そういうところまで求めている作品ではないのかもしれませんが、そこまで考えさせられる作品と言っていいのではないでしょうか。
問題は「彫った痛み」の解釈にあると思います。「観音様」を「彫った痛み」ともとれますが、どうも違うようです。「女」が何かを具体的に「彫った」のか、精神的に何かを比喩的に「彫った」のか、そこがここからは読み取れませんでした。そういう読み方をするよりも、読者が自分自身にあてはめて考えなさい、ということかもしれませんね。あるいは、そういう〝解釈〟をせずに感じよ!という見方もできると思います。小品ながら、考えさせられる作品だと思います。
| ○総合文芸誌『中央文學』456号 |
 |
| 2001.10.25
東京都品川区 日本中央文学会発行 600円 |
めまい/寺田量子
横たわって 闇の中 みひらくと
しろい輪になって浮き上がる蛍光ランプが
左右にかなりの速さで動き回る
走っているのはランプじゃなくて 私のめまい
気づいて間もなく眠りにおちた
さめたとき もうランプは動かなかった
起き上がって 歩いてみると ふらつくけれど
気分はよくなっていた
こどものころ 眠ろうとして目をつぶると
花のかたちや星や小鳥が 踊ったり 万華鏡に似てうつりかわり
隣に寝ている兄と 何がいま見えているか話し合った
いまも隣に 兄がいたら こどもに帰って
走るランプではなく 花園がひらけ
その中に坐っているだろうか
そう思うと めまいも楽しくなった
「気分はよくなっていた」と「そう思うと めまいも楽しくなった」というフレーズがうまく呼応している作品だと思います。「めまい」は通常は病気への前兆で好ましいものではありませんが、作者はそれさえも楽しんでしまおうという旺盛な意欲を持っているようで、逆に読者が励まされてしまいます。その意欲が実は「隣に寝ている兄と 何がいま見えているか話し合った」ことに起因していると判ったとき、言い知れぬ安堵感と淋しさを感じさせるのは、なぜなんだろうと考えています。
おそらく、男と女という区別がなかった「こどものころ」を、読者である私も思い出しているからかもしれません。妹とも、親戚の従姉妹とも「隣に寝ている」状態にあった頃へのなつかしさかもしれませんね。ある時期を境に許されない行為となったのは大人になった今は理解できますが、血のつながりがあるとはいえ異性と同室であるときめきがあったように思います。女性である作者とは違うのかもしれませんが、この作品を読んで私はまずそれを思い出しました。その上で、兄弟姉妹への人間の本質的な愛情を感じています。古典的と言ってしまえばそれまでですが、こんな世の中になってみると、こういう〝古典的〟な愛情に回帰する必要もあるのではないか、そんなことも考えさせられました。
その2 その1へ
![]() (10月の部屋へ戻る)
(10月の部屋へ戻る)
![]()